前節では、死後を因果の論理を使い、論理的に解明した。仏教では、論理的に死後を説明するとともに、具体的な有り様も説いている。前節が論理で理論的枠組みを形成したとするならば、本節は心の徹底的な洞察によって人間の本性を明らかにし、理論と矛盾ない死後を記述するものである。
章ー節ー項
ex. 1-2-3 → 第1章の中の第2節の中の第3項
ex. 1-2 → 第1章の中の第2節
第1節:仏教の説く死後(理論)
第1項:因果の道理
第2項:無我と空
第3項:唯識
第2節:仏教の説く死後(具体) ←現在地
第1項:理論の補足
第2項:六道輪廻とその原因
第 1 項:理論の補足
具体的な死後の世界と第 1 節の理論を矛盾なく記述するために、第 1 節の内容にいくつか付け加えることがある。
まず、善悪因果応報についてである。我々の行いである身口意の三業には、それぞれ善・悪・無記199という三つの性質(三性)がある。楽(幸せ)という結果を引き起こす行いを善業、苦しみという結果を引き起こす行いを悪業と言う。善悪どちらの性質でもないものは無記と言われる。そして自分のやった行いは全て自分にそれ相応の結果として返ってくる。
故に、現在、幸せ(苦しい)ならば、それは過去にそうなるような善い行い(悪 い行い)をしたからであり、今、善い行い(悪い行い)をしているならば、必ず 将来幸せ(苦しみ)になるのである。これは世間一般でも自業自得、自分の得た 結果は自分のした行い(業)によるということは知られている。自業自得は、善 い運命だろうが、悪い運命だろうが、全ての原因は自分にあるということであり、これに例外を認めないのである。これは信じる、信じないの次元ではなく、全て の人に例外なく迫るものである。そのため、仏教では、因果の道理をあきらかに 見て、決して撥無してはならないと教えられる。そのことを道元は『正法眼蔵』 の「深信因果」にこのように言う。
仏法参学には、第一因果をあきらむるなり。因果を撥無するがごときは、おそらくは猛利の邪見をおこして、断善根とならんことを。おほよそ因果の道理、歴然としてわたくしなし。造悪のものは堕し、修善のものはのぼる、毫釐もたがはざるなり
正法眼蔵
善悪因果応報の道理は、単に道理として教えられたわけではない。悪いことを止め、善いことをしなさいという止悪修善の教えとして説かれたのである。このことは「諸悪莫作、衆善奉行、自浄其意、是諸仏教」( 七仏通戒偈)として知られている。
では、何が善で何が悪なのか。我々が三業によって造る悪を十に整理されたものが十悪( 十悪業)である。これらの頭に不をつけたものが十善(十善業)と言われる。詳細は省くが、三業によって、我々は善悪を行っている。 次に、善悪の業がいつ結果として現れるかという時期について説明を加える。善悪の行為はそれぞれ業種子となり、阿頼耶識に熏習されるのであるが、それらが結果として現れるには時間がかかるものもあれば、すぐに結果となって現れるものもある。それを受ける時期によって三種に分け、三時業と呼ぶ。報われるのが現世であるような業を、順現法受業( 順現業・順報業)と言い、報われるのが次の生であるような業を、順次生受業(順生受業・順生報)と言い、報われるのが来世の次の生以後であるような業を、順後次受業(順後業・順後報)と言う。つまり、我々が今受けている結果は、この世に生まれてから現在までの業による結果だけではなく、生まれる前の過去無量劫からの業による結果も受けているのである。順現業、順次業、順後業は受ける時期が決まっているため定業という。これに対し、時期の定まらないものを不定業( 順不定受業)といい、三時業に加え、四業という。
業は、大きく引業と満業という区別もなされる。引業とは、ある結果を生じる行為( 業)の中でも、総体的に結果を生じさせる業である。その結果において、内容づけ、個々の区別を与える業を満業と言う。前世の業の中でも、生を受ける世界( 人間に生まれるなど)を生じさせる業が引業であり、賢愚美醜( 六識)を生じさせる業が満業である。また、第 1 節の最後に少し触れたが、共通するような果報を引き起こす業を共業と言い、個々に固有な果報を引き起こす業を不共業と言う。
第 2 項:六道輪廻とその原因
我々が死んだなら、輪廻すると仏教は説く。輪廻とは、六道を生まれ変わり死に変わりするということである。六道とは、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天の六つの世界のことである。地獄・餓鬼・畜生を三悪道と言い、それと対比し修羅・人・天は相対的に苦しみが少ないため三善道と言うが、これら六つの世界は全て苦しみの世界であることに変わりはない。苦しみは地獄が最も大きく、次いで餓鬼・畜生・修羅・人・天である。六つの世界と言っても、これらの世界があるわけではなく、我々の業に従い、阿頼耶識によって生み出される世界である。故に、それぞれの阿頼耶識ごとの世界があるのであるが、大きく分けると、この六つになる。我々は引業によって、今人間界に生まれ、共業があったため同じ世界を見ている。しかし、それぞれ同じ人間ではないのは、満業が異なるからであり、不共業のためにそれぞれ異なる境涯に生きるのである。そして、死んだならば、再び引業によって六道のどこかに生まれるというわけである。 六道を輪廻する仕組みは分かったが、なぜそもそも六道輪廻しているのか。それはそのような悪業を造っているからである。では、なぜ悪業を造るのか。その原因を仏教は煩悩とみる。煩悩とは、我々の身心を煩わせ、悩ませ、汚す精神作用の総称である。煩悩( 惑)が原因となり、悪い行いをし( 果)、悪業( 因)は苦果をもたらす。生じた苦果により( 因)、再び迷いが生じる( 果)。「且つ因、且つ果、虚僞相襲ぬ200」で、因果の連鎖の泥沼から出られない。その有様はまるで尺取虫が同じところをぐるぐる回り循環しているかのごとくであり、蚕が自らの糸により繭を縛るかのごとくである201。これを惑業苦という。惑業苦の連鎖で、我々は迷いの世界(六道)に繋ぎ止められる。
煩悩の中でも諸煩悩の根本となるもののことを根本煩悩という。その根本煩悩に伴って従属的に起こる煩悩を枝末煩悩(随煩悩)という202。以下では、枝末煩悩の説明は省き、根本煩悩の説明をする。
根本煩悩は、貪・瞋・痴・慢・疑・悪見の六つである。貪とは、貪欲とも貪愛ともいい、好む対象への強い執著、激しい欲求、むさぼり求める心を起こすことである。瞋とは、瞋恚のことで、怒ることである。貪が心にかなうことに向かって起こるのに対し、瞋は心にかなわないことに向かって起こる。火にたとえられることが多く、煩悩の中でも最も激しく善心を汚し、仏道の妨げになると言われる。痴とは、愚痴とも言い、愚かで道理に関して暗いため的確な判断ができず、迷い惑っていることである。貪・瞋・痴の三つは、衆生の善心を害する最も根本的なものであるから、三毒とか三不善根と言われる。慢とは自他を比較し、他を軽蔑し、自己に驕り高ぶることをいう。倶舎論では、七慢として七種に分類される203。疑は、仏教の教えに対する躊躇のことを指す204。悪見とは、悪い考え、誤った見解のことで、五つに分けられ、五見とも言われる。
これら煩悩は、唯識で心所に分類され、心の作用と見なされる。心所の拠り所とされるのは八識で、心の中心となることから心王と呼ばれる。煩悩は心で起こり、それが三業になって現れるのである。三業と言っても、仏教で重視されるのは意業、心での行いである。なぜなら、「考え、決断するのは思業、実行にうつるのが思已業で」あるからである205。確かに、我々が何か行動するのは、意識・無意識に関わらず、心で思っていることであろう。口や身体での行為だけから理解すれば、それほど悪いことはしていないように思われる。しかし、心を見つめれば悪ばかりではないだろうか。「一人一日中に八億四千の念あり。念念の中に作す所、皆是三途業といえり206」と言われるが、毎日心で思っていることの量は数え切れないほどの量で、それは善いことばかりではない。苦しみの世界を永遠と彷徨っていると言われても仕方のないことである。
厳密に言えば、我々が六道四生207を輪廻している根本原因は煩悩ではなく、無明である。無明とは、真理に暗い不如実智見のことである。真理とは仏教の道理のことで、因果の道理、空、唯識を通して真実の世界を明らかにしているにも関わらず、それが分からないということが無明なのである。無明は、煩悩の一つとしての無明と煩悩の根本としての無明に分けられる。唯識宗では、前者を相応無明、後者を不共無明と言い208、大乗起信論では、前者を枝末無明、後者を根本無明と言った。輪廻の原因としての無明は、根本無明のことである。この根本無明は、無始無明とも言われ、始まりのない始まりから存在するものである。
何が故に衆生は六趣に輪廻し、生死を断たざる。答えて曰く、衆生は迷妄にして無心の中において妄りに心を生じ、種々の業をつくって六趣に輪廻せざるはなし。209
無心論
無始無明を根本にし、煩悩によって惑業苦の連鎖で六道を輪廻しているのが我々の本当の姿なのである。
脚注
199 無記とは、善とも悪とも区別されないもののことである。
200 曇鸞、『往生論註』( 大正蔵 四〇・八二八 a)
201 曇鸞、『往生論註』( 大正蔵 四〇・八二八 a)
202 根本煩悩、枝末煩悩という分け方は、主に倶舎宗、唯識宗でなされる。
203 八慢、九慢と分類されることもある。
204 なお、浄土教では大無量寿経に基づき、自力の心を疑という。
205 竹村牧男、『唯識の探求』、p.158
206 法然『拾遺黒谷上人語燈録』( 大正蔵 八三・二四五 b)
207 四生とは、生物の生まれる四種の形式で、胎生(母胎から生まれる)、卵生(卵殻から生まれる)、湿生(湿気から生まれる)、化生(忽然と化成する) のことである。
208 不共無明は独頭無明とも言われ、煩悩とは相応せずひとりで起こる。
209 菩提達磨『無心論』( 大正蔵 八五・一二六九 b)

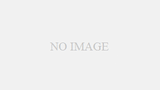
コメント