この「幸福論の再考」は、当サイトの管理人が卒業論文として提出したものを元に、論文からより一般的な文章表現に変え、最新の研究も盛り込みながら、できるだけ老若男女誰にでも理解できるように、レーゾンデートル(人間の存在意義)について書いたものである。この内容は一度書いて終わりというわけではなく、論のつながりや細部は定期的に見直しをかける予定である。
当サイトの管理人である私は、どちらかというと「人生ハッピー♪」ではなく、「自殺したい」という気持ちが分かる側だと考えている。これは今がとてつもなく辛いからというよりも、このまま生きていって本当に幸せなのか?という考えの方が強いから、になる。しかし、どんな場合にせよ、「本当に自殺してしまって良いのか?」と再考してみることは有意義だと考える。
元々、卒業論文のテーマのきっかけは、「自殺」であった。大なり小なり、どんな人でも、小さなときから大人になってからも、一瞬もしくは長い時間、「自殺」について考えたことはあるのではないだろうか?令和3年の年間の自殺者数は2万人、これでも10年以上前に比べれば1万人減った方だが、1日あたり54人が自殺している計算になる。先進国の中では韓国に次ぐ2番目の自殺大国であり、G7では1番である。また、2021年時点で、WHOが言うには年間70万人以上が世界で自殺しているという。これは45秒に1人が世界のどこかで自殺をしている計算となる。この事実は、「命は尊い」という言葉では自殺は止められないということを表しているのだと考える。当サイトは、決して自殺を止めるために作ったわけではなく、「本当に自殺をすることが最善策なのか?自殺をしなくてもいいような意味は人生にあるのか?」を考えるために作った。
さて、この試みの最終目的は、「人生の意味とはどのようなものであり得るか」、また、「それを満たすものはあるかどうか、あるとすればそれは何か」、を考え、できるだけ多くの人が最も満足のいく結論を出すことである。
人生の意味は、言葉の意味が人によって変わるため、これまで様々なレベルで人生の意味論が唱えられてきた。雑誌・一般書に書かれるレベル、学問的な立場から書かれるレベル、宗教・スピリチュアル的な立場から書かれるレベルなどである。そのため、本論では、①近年の分析哲学における成果を踏まえ、「人生の意味」が意味するところを定義し、②その定義を満たす人生の意味は何かを実存哲学、仏教哲学から学術的に論じていく。ただし、当サイトの内容は論文として提出するものではないため、できるだけ平易な言葉や解説も用いつつ、どのような人でも合点がいくように論を展開していくことにする。
学術的に述べるために、論理と批判的観点を重視し、一つの事柄に対して出来るだけ複数の視点から考える。この際に扱うのは、西洋哲学と東洋哲学(仏教)である。この二つはそれぞれ論理を基盤として議論を行うためである。
しかし、扱っている対象が少し異なるため、同時に扱うことは難しい。前者は、物質・精神などを個々人から離れて扱うのに対し、後者は、それらを主体から切り離せないと考え、個々人の内面の奥深くまで思索を繰り広げるのである。筆者の考えでは、上記から、西洋哲学が言及できない点にまで仏教哲学は論理を張り巡らせ言及している。したがって、本論では、西洋哲学から始まり、それを補完するものとして仏教哲学を扱い、人生の意味論を展開していく。
本論の価値は学問的価値と社会的価値の二つがあると考える。学問的価値は、西洋実存主義、中でも、死によって人生は無意味になるという実存主義者にとって、本論は新たな視点を与えると思われる。本論で提示する仏教哲学からの視点は、実存哲学で直面する死の問題の解決につながるかもしれない。次に、社会的価値は、フランクルの言う実存的空虚で悩まされる人々にとって、本論文で明らかにする人生の意味が救いの手になるかもしれないということである。そして、毎年自殺する多くの人に自殺以外の選択肢はないのか?という提案が可能かもしれない。
本論の構成は以下の通りである。
第 1 章では、まず人生の意味の言葉の定義を、先行研究を元に行う。次に、人生の意味を考える必要性について論じる。そして、人生の意味を幸福という観点から、どのような幸福であれば人生の意味と言えるのかを考える。
第 2 章では、死を客観的側面と主観的側面から考え、死と人生の意味がどのように関連するかについて論じる。その上で、死を考える時、死後に関する言及が必要になることを示す。
第 3 章では、まず死後の有無を仏教の理論から論じ、その論理から外れない具体的な内容を記述する。
第 4 章では、前章までを踏まえて、人生の意味とは何かをまとめる。
幸福論と自殺は、一見違う話のように見えて、同じ内容を論じることになる。しかし、この論のつながりは考える必要があるため、まずは幸福論から記事を更新していくことにする。(2023年1月)

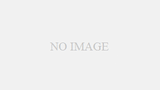
コメント