章ー節ー項
ex. 1-2-3 → 第1章の中の第2節の中の第3項
ex. 1-2 → 第1章の中の第2節
第1節:生と死の関係
第1項:人生における死とは
第2項:死をどのような観点から考えるか
第2節:死の客観的側面
第1項:死の人称性
第2項:死の持つ性質
第3項:人間の状況
第3節:死の主観的側面
第1項:死の主観的側面を考える際の三つの立場
第2項:生前に感じられる死
第3項:臨終に感じられる死
第4節:死から死後の問題へ
第1項:死によって人生は無意味になるか
第2項:実存哲学と仏教の死の捉え方の違い
本節では、死は人生を無意味化するという考えについて吟味する。また、第 2項で本章全体をまとめる。
第 1 項:死によって人生は無意味になるか
本項では、死によって人生が無意味になるという主張について考える。この主張は、言葉を補うと、「死によって無になるから、人生は無意味になる」と書き直すことができる141。死によって無になる、とは言い方を変えれば「死後は無い」という考えである。なぜ、死後が無いならば人生は無意味になると言えるのか。
例えば、サルトルは音楽になぞらえて次のように言う。
(あるメロディの)最後の和音は、当のメロディーたるこの存在充実に付着している。もし最後の和音がないならば、このメロディーは宙にとどまるであろう。そして、終末のこの未決定は逆流して音符から音符へとさかのぼり、それらの音符のおのおのに未完の性格を与えることになるであろう。死は、つねに-この考えかたが当を得ているか否かは、いまだわれわれの決定しうるかぎりではないが-人生の終末と見なされてきた。死がかかるものと見なされるかぎり、或る哲学が、ことに、人間をとりまくところの絶対的に非人間的なものに対して、人間的な立場を明確ならしめることに専念する哲学が、まず第一に、死を、「人間存在の無」へ向かって開かれた一つの扉と見なすのは、当然なことであった。また、この無が、或る意味で、存在の絶対的な停止、もしくは非人間的な形態のもとにおける存在であると考えられるのも、当然なことであった。142
サルトル
メロディにおいて、最後の和音はメロディの存在を意味づけるものであり、それがなければメロディ全体が宙にとどまる。同じようにその人の死は、人生の最終末端であり、その人の存在に意味を付与するものとしてあるとすれば、死によって無になることは人生の意味を無にするものとして考えられるのではないだろうか143。逆に、死によって、むしろ人生を完成させられるということも考えられる。すなわち、自分の死に方を考え、自分の思うように死に、まさに有終の美を飾れるならば、その死は最後の和音を為すのではないか。これについて、サルトルはこのように反論する。
私は、私の死の瞬間が私自身によって定められるのではないということ、宇宙のもろもろの因果関係がそれを決定するのだということを、はっきりと知っている。そうだとすれば、われわれは、もはや、死が人生に外から一つの意味を付与する、などと言うことができない。一つの意味は、主観性そのものからしか、やって来ることができない。死はわれわれの自由を根拠としてあらわれるのではないから、死は、あらゆる意味を人生から除き去ることしかできない。144
サルトル
死が無規定に、暴力的にやってくるため、我々には死を選ぶ自由などない。だから、自分の望む死はやってくることはないのである。続けてサルトルは、自分の将来に期待して生きてきたが、結局一冊の本しか出せず、死んでしまった作家を例えとして出し、このように言う。
それらの総体-個々の行為、もろもろの期待、もろもろの価値-は、一挙に、不条理のなかにおちいる。それゆえ、死は、決して、人生にその意味を与えるところのものではない。むしろ反対に、死は、原理的に人生からあらゆる意味を除き去るところのものである。もしわれわれが死ななければならないならば、われわれの人生は意味をもたない。というのも、人生の諸問題は何らの解決をも得ることがないし、それらの問題の意味そのものが未決定のままにとどまっているからである。145
サルトル
サルトルの論理はこうである。「死は無規定にやってくる」、だから万全な準備をする間もなく、すべてに満足する前に、何らかの後悔を残しながら我々は死んでいかなければならない。しかも、それまで人生でしてきたことは生きている時には意味が感じられたとしても、「死によって無になる」以上、意味も無化する。だから、人生は無意味である。
カミュもサルトル同様、死により人間は無になるということから人生の不条理を描いている。
死という予測不能な出来事の、こうした基本的で決定的な側面が、不条理な感情の内容をなしている。死というこの宿命の破滅的な照明を浴びると、無益という感情があらわれる。ぼくらの在り方を定める苛酷な数学をまえにしては、いかなる道徳も、いかなる努力も、先験的に正当なりとすることはできないのである。146
カミュ
1 が 0 になるという数学の前に、人生の価値を正当化できるものは存在しな い。0 になることが決まっている存在にいくら価値を付けようと躍起になっても、
「無益」としかカミュ自身は感じることができなかったのである。
ショーペンハウアーは人生自体が苦しみ、不条理の連続であるから、死によって無になるのならば、死を選ぶべきだと明言する。
どのような人間の生活も、これを総観すれば、悲劇としての性質を帯びている。人生というものは、通例、裏切られた希望、挫折させられた目論見、それと気づいたときにはもう遅すぎる過ち、の連続にほかならないことが、知られるのだ。147
ショーペンハウアー
もしも死によって全くの無になるのだということがたしかだとしたら、世の中がこのような性質のものである以上、無条件に死を選ぶべきものであろう。148
ショーペンハウアー
ここで「死後は無いから、人生は無意味になる」という主張について考えてみると、この主張をする論者が反論しているのは「死後がある」という意見ではない。死後が無いという前提に立っているため、死後が有るということ自体がナンセンスになるからである。彼らが反論しているのは、「死後は無いとしても、人生に意味はある」という意見である。分かりやすく言うと、「死によって我々は無になる。しかし、だからこそ今の人生はかけがえのない意味を持つのではないか」ということである。だが、この二つの主張はどちらが正しいと言うことはできない。それは「死によって無になる」、「死後は無い」という証明がなされていないからである。したがって、これらの主張は、まとめて次のように書き換えられる。
以上より、死によって人生は無意味になるという考え方は必ずしも取ることはできないということが分かった。
第 2 項:実存哲学と仏教の死の捉え方の違い
本章では、主に実存哲学から、死の問題を考えた。実存哲学の死の捉え方は、 仏教の死の捉え方とは、異なる。すなわち、本章で扱った実存哲学者たちは、生 れてから死ぬまでの今生だけを見て、人生の意味を考えるのに対し、仏教では、 死は終わりではないと考え、悠久の生命の流れの中での人生における意味を考 えるからである。今生だけを見れば、死で今の生は終わり、それまで手に入れた ものは全て失われるため、人生には意味が無いという考え方もとることはでき る。つまり、死後があろうがなかろうが、100 年の人生だけを考えると、人生は 無意味になりうるのである。もし、人生が無意味にならないとすれば、今の生が 死後と関わりを持たなければならない。その上で、人生に意味はあるのかどうか、あるとすれば何なのかが論じられる必要がある。そこで、次章では、死後がある のかないのか、死後は人生とどう関わりを持つのかを論じる。
脚注
141 「死は全てを奪うから、人生は無意味になる」とも解釈できる。それについては、次項で検討する。
142 サルトル、『存在と無』、p.259
143 サルトルは、一方では、最後の和音は沈黙で作られている、すなわち、無も意味を構成している存在だという見方もできると言っている。ここでの前提は、終末としての死は人生に意味を付与する、もしくは取り除くということである。この前提は必ずしもそうとは言い切れない。
144 サルトル、『存在と無』、p.277
145 サルトル、『存在と無』、pp.277-279
146 カミュ、『シーシュポスの神話』、pp.32-33
147 ショーペンハウアー、2011、斎藤信治訳、「生きんとする意思の肯定と否定に関する教説によせる補遺」、『自殺について 他四篇』、岩波文庫、p.98
148 ショーペンハウアー、「自殺について」、『自殺について 他四篇』、pp.77-78

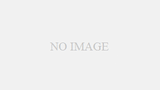
コメント