章ー節ー項
ex. 1-2-3 → 第1章の中の第2節の中の第3項
ex. 1-2 → 第1章の中の第2節
第1節:仏教の目的
第2節:仏教の目的は人生の意味になるか
第3節:結論と課題 ←現在地
本節では、本論全体を概観し、結論をまとめ、今後の課題を述べる。
まず、第 1 章である。第 1 節では、人生の意味の言葉の定義をした。本論で扱う人生の意味とは、「私が人間に生まれ、生きていく究極の目的は何か」という問いであり、その問いに答えを与えるものである。第 2 節では、そのように定義される人生の意味は問われることがあるのかを検討し、第 3 節では、そのような人生の意味を本論で扱うことが有意味かどうかを考えた。そして、人生の意味かどうかを判断するために、本論で扱う人生の意味の必要条件を第 4 節で挙げた。すなわち、人生の意味と言えるためには、「主観的かつ客観的に納得できる」、「生まれたことを肯定できる」、「絶対的な意味を持つ」ことが必要条件として考えられる。第 5 節で、これらを満たすものとして幸福について考え、自足的な幸福が必要条件を満たすものではないかと提示した。しかし、自足的な幸福だけでは、具体性に欠けるため、それがどのような幸福であるのかを明らかにしたい。そこで、「絶対的な意味を持つ」という必要条件を「最悪の状況でも揺るがない」と言い換え、人間にとって最悪の状況と思われる「死」を手がかりにすることにした。
第 2 章では、死が我々の幸福にどのような影響を与えるかを考えた。まず、第 1 節で本論での死を扱う立場を明確にした。第 2 節は、死を客観的に観察し、死の持つ性質を浮き彫りにした。そのような性質を持つ死は主観にどのような影響を及ぼすのかを第 3 節で推測した。第 4 節では、死に関する二つの大きな主張について、議論した。第 3 節と第 4 節の結果、死が我々の幸福にどのように影響を与えるかは、死だけを考えていては分からず、死後の有無も考えなければならないことが分かった。
第 3 章では、死後は有るのか無いのかを考えた。まず第 1 節では、論理的に死後の有無を明らかにするために、因果律を使った。その結果、死後は無ではなく、何らかの意味で有(実体として有ではない)である必要があることが分かった。この理論に矛盾しない死後を仏教は具体的に説いており、それを第 2 節で詳述した。結局、我々の死後は、人間の本性と因果律を結びつけることで苦しみの世界にいくということが理解された。
第 4 章の第 1 節では、前章を踏まえて、六道を離れることが人間に生まれた意味であるとする仏教の目的についてまとめた。続く第 2 節でそれが本論で定義した人生の意味の答えになるかどうかを必要条件に照らし合わせて考えた。
結論として、「私が人間に生まれ、生きていく究極の目的」とは、「無始より流転してきた肉体ではない本質の私が、輪廻から解脱し、涅槃をうるために、現生で正定聚に入ること」である。ただし、これは仏教の立場からは全ての人の人生の意味になるが、個々人の立場からは仏教を論理と感情の両面で納得出来る人のみ人生の意味となる。
本論では、人生の意味が何かを考えることに重点を置いたため、どのようにしてその人生の意味が達成されうるかまでは述べることができなかった。また、一つ一つの主張を詳しく吟味することもできず、概論のようになってしまっている。特に、仏教以外に、本論の定義や条件に合う人生の意味がないかを考えることは必要である。今後の課題は、本論で述べた人生の意味を達成する道のりを示すことと、章・節・項それぞれの厳密な吟味をすることである。そして、社会に還元する方法を考え、実現させることも大きな課題であると思われる。

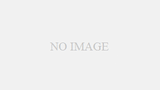
コメント