第 1 章で定義した人生の意味と、必要条件を再掲示する。
仏教の目的が①~③の条件を満たすならば、仏教の目的は、一先ず人生の意味と言うことができるであろう。それぞれを順に考えていく。
まず、①についてである。客観的な納得とは、論理のことであるから、死後の世界を論理で説明し、六道から出離することが人生の意味であるということには問題はないように思われる。主観的な納得とは感情のことであり、自分自身が「それが人生の意味だ」と納得できるということである。これをキルケゴールの言うような「私がそのために生き死にできる」という意味で解釈するならば、仏教の目的は、今を逃せば永遠と苦しみの世界を彷徨うことになる一大事を解決することであるから、仏教を信じる人にとっては満たすであろう。しかし、仏教でどれだけ論理や具体的なことを挙げて、真実と言われることを説かれていても、それを信じなければ六道出離と聞いても夢物語のようになってしまうため、仏教を信じない人には人生の意味と思えないかもしれない。
ここで仏教を信じるとはどういうことかを考えてみる。仏教の最も基本的な 教えは因果の道理であり、因果の道理から離れた教えはないのであった。という ことは、仏教を信じるということは、因果の法則を信じるということであり、因 果の論理を信じるということである。逆に仏教を信じない人は因果の論理を信 じない人ということである。因果の論理を理解し、それが正しいと思えるならば、それは仏教を信じるということに等しい。また、仏教は因果の論理で死後の世界 についての理論を形成している一方で、具体的な死後の世界にも言及している。この具体的な死後の世界は、心の徹底的な洞察を元にして説かれており、因果の 論理の重圧にも耐えうるものである。しかし、人間の心に関する内容(煩悩等) を受け止めることができない、もしくは分からない人にとっては、飛躍している ように感じられるかもしれない。したがって、仏教を信じるということは、因果 の論理と心の洞察が分かるということであり、仏教の目的が六道出離というこ とを理解できるということであり、それが人生の意味と納得できるということ である。反対に、因果の論理、心の洞察を理解できない人は、仏教の目的を人生 の意味とは納得できないであろう。
次に②についてである。仏教の目的は、単にこの世だけでなく、無始から流転し続け、今後も永遠と流転し続ける私の多生の目的であるから、その目的を達成したならば、「本当に生まれてきてよかった。このために生まれてきて、今まで生きてきた。これから生きていても満足だし、いつ死んだとしても後悔することはない」と言えるであろう。釈迦の弟子である舎利弗は、無量無辺不可思議劫の後に仏になるという予言を聞いて、歓喜したという218。まして、死後、仏になれることが定まっているのが正定聚であるから、歓喜は当然といえば当然である。
最後に③である。正定聚の位は、不退転位と言われ、絶対に退転することがない。退転とは、証ったはずの位を失うことである。正定聚はそのようなことがない位であり、どのようなことが起こっても決して揺らぐことのない位である。すなわち、死を目の前にしても、恐怖や不安で揺らぐことは絶対になく、死んだら涅槃に入るということが分かっているのである。故に正定聚の位に入るということは絶対的意味を持つと言えるであろう。また、涅槃の境地は、我々が欲によって満たす幸せとは次元が異なり、その幸せは不可称不可説不可思議と言われ、言葉にすることも説くことも想像することもできないと言われる。我々が理解できるのは言葉によってであり、比較する相対的な次元においてであるから、この涅槃の境地は絶対的なものと考えられる。
以上をまとめると、仏教の目的は、本当は全ての人に共通の人生の意味なのだが、仏教を信じない人はそれが人生の意味であるとは思えないため、人生の意味にはなり得ない。一方、仏教の論理を理解できる人にとっては、仏教の目的=人生の意味となり得る。
脚注
218 『法華経』譬喩品第三

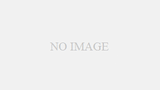
コメント