章ー節ー項
ex. 1-2-3 → 第1章の中の第2節の中の第3項
ex. 1-2 → 第1章の中の第2節
第1節:仏教の目的 ←現在地
第2節:仏教の目的は人生の意味になるか
第3節:結論と課題
第 3 章で、我々は死んだら苦しみの世界を永遠と生まれ変わり死に変わりすることを示した。その原因を取り除き、六道から出離することが仏教における人間に生まれてきた究極の目的である。六道から出離したことを解脱とか涅槃と言われる。解脱とは、「束縛から解き放す」ということで、煩悩から解放されることを言う。涅槃とは、「煩悩の火が吹き消された状態」であり、解脱したならば、煩悩は二度と起こらないため、語義上は解脱も涅槃も同義である。
涅槃は大きく二つに分かれる。有余依涅槃と無余依涅槃である。有余依涅槃とは、涅槃に入っていても身体が残っている涅槃である210。釈迦は 35 歳で成道後、 80 歳で入滅するまで、身体を備えていたため、有余依涅槃であった。一方、無余依涅槃とは、肉体からも完全に解放された涅槃であり、釈迦は死とともに無余依涅槃に入った。さらに大乗仏教では、無住処涅槃を説く211。これは、生死を離れ、涅槃の境地に入りながら、あらゆる人々を救済するために涅槃の世界にとどまらず、活動する境界である。大乗仏教は、この無住処涅槃を究極の目的としている。「その身は生死輪廻の境界の中にありながら、しかもそれを超越して自由の境地を得ている」212。
無住処涅槃は、我々が死んでから入ることのできる境地である。というのも、 身体を備えている以上、我々は煩悩から離れきれないからである。それどころか、煩悩は死ぬ最後の瞬間まで、減ることもなく、一瞬でも止まることすらないと言 われる。
「凡夫」というは、無明・煩悩われらが身にみちみちて、欲もおおく、瞋り腹だち、そねみねたむ心多く間なくして、臨終の一念に至るまで止まらず消えず絶えず213
親鸞
故に、人間のことを煩悩具足と言われる。具足とは、「みち備わる」ということで「完全」という意で使われる。したがって、我々は完全な煩悩ということである。だから煩悩成就(煩悩で出来上がっている)とも言われる。
では、死んだ人は皆煩悩がなくなって涅槃の境地に入るのであろうか。それは六道を流転し続けているということに矛盾するため違うであろう。生きている時に死んだら涅槃に入る確約をされている人のみが、死後、六道を出離できると考えるのが妥当であると考えられる214。しかも、生きている時に確約されていなければならないから、煩悩はなくならないままである。これを曇鸞は、「不断煩悩得涅槃分215」と表している。涅槃分とは、涅槃に至る位ということである216。正定聚とか正性決定とも言われ、まさしく悟りが決定している人(位)のことを指す。我々が煩悩を断たずして、涅槃に入る確約をされる境地があるということである。
以上を簡潔にまとめると、我々の人間に生まれてきた目的を大乗仏教では「正定聚の位に入ること」とする217。では、仏教で言われる人間に生まれてきた意味は、第 1 章で定義し、条件付けした人生の意味に相応するのだろうか。そのことについて、次節で考える。
脚注
214 服部純雄、1983、「『往生論註』における「得涅槃分」の一考察」、『印度學佛教學研究』、32 巻 1 号、pp.128-129
215 曇鸞『浄土論註』( 大正蔵 四〇・八三六 c)
216 涅槃と同じ意味で使われることもある。
217 正確に言えば、大乗の中でも浄土仏教である。

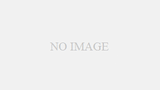
コメント