章ー節ー項
ex. 1-2-3 → 第1章の中の第2節の中の第3項
ex. 1-2 → 第1章の中の第2節
第1節:生と死の関係
第1項:人生における死とは
第2項:死をどのような観点から考えるか
第2節:死の客観的側面
第1項:死の人称性
第2項:死の持つ性質
第3項:人間の状況
第3節:死の主観的側面 ←現在地
第1項:死の主観的側面を考える際の三つの立場
第2項:生前に感じられる死
第3項:臨終に感じられる死
第4節:死から死後の問題へ
第1項:死によって人生は無意味になるか
第2項:実存哲学と仏教の死の捉え方の違い
第 1 項:死の主観的側面を考える際の三つの立場
死の主観的側面を考える際に、大きく三つの立場・段階があると思われる。まず、死に面していない時の死の主観的側面、次に死が差し迫り自分のこととなっている場合の死の主観的側面、最後は今まさに死んでいくとき(臨終)の死の主観的側面である122。死はずっと同じように感じられるのではなく、それぞれの段階で異なって感じられるのではないだろうか。
自分が死に( 今まさに)面していない場合123、死はあくまで想像であり、他人の死以外は分かっていない。死に面していない人の中には、死を漠然と怖いものと思っている人もいれば、死を詳しく研究している人もいるだろう。どれだけ詳しく死について学んでいる人であっても、死を理解していることとは異なる。死について理解するとは、前節のようなことを理解することであり、それが分かったから死が分かるとはならないのである。
このことは自分が死に(今まさに)面している場合も同じである。この場合、面していない時よりも死の不安や恐怖がより一層感じられる。しかし、実際に死を経験しているわけではないので、死を想像して恐れているにすぎない。
第三の今まさに死んでいく状況では、それまでの不安や恐怖は極限に達すると考えられる。同時にそれまで考えていた死は、実際の死とは大きく異なるということが感じられると思われる。
このように第 2 節で扱った客観的な死の性質は、その状況によって主観的にそれぞれ違って感じられると考えられる。なぜそのように言えるのかを大きく生前(先の二つをまとめた)と臨終の二つに分類して考える。124
第 2 項:生前に感じられる死
死をどのように感じるか、主に恐怖(不安)125という感情から考える。これは、死に対する恐怖と死後に対する恐怖の二つに分けられる。死への恐怖とは、死による肉体的苦痛と死による精神的苦痛に対する恐怖である。死による肉体的苦痛とは、死ぬまでにもしくは死ぬ時に肉体に訪れる苦痛のことである。まだ生きている時には、自分がどういう風に死んでいくかということを想像する。「事故で死んだら痛いだろうし、癌は抗癌剤で大変だ。死ぬなら健康な時にポックリ死にたい。」これは死が訪れるまでに、もしくは死んでいく時に自分の肉体にかかる苦痛に対して恐怖を抱いているのである。だから、PPK(ピンピンコロリ)を幸福に老いる条件として願う人も多い126。苦しみも痛みもなく死ぬことができたら幸せというわけである。この死による肉体的苦痛は、前項の性質から考えると、死は確実にくるもので(確実性)、誰も交代はできないものであり( 代理不可能性)、経験したことがないため( 追い越し不可能性)、その時の苦痛を想像して恐怖を感じるのである。
死による精神的苦痛とは、死ぬことで自分の大切なものを失ってしまうのではないかという精神的な苦しみである。死とは不可逆性のものであるから、もう一度戻ってくることはできない。今持つものは全て自分から手放さねばならない。お金、地位、名誉、才能、家族、死ぬ時に一緒に連れ添うことができるものは何一つないのである。しかし、我々には執着する心があるから、今まで手に入れたものは全て我が身から離れていくと分かると、我々は恐怖を感じる。財布を失くしただけで怖くなるのだから、全てが失くなると分かれば尚更である。いつかは分からないが(未規定性)、いつか必ず(確実性)、自分の所有しているもの全てと別れなければならず( 没交渉性)、その苦痛を想像して恐怖を感じるのである。
次に、死後への恐怖( 不安)とは、自分が死んだら周りは大丈夫だろうかという身辺に対する不安や、死んだら無になるのか、それともどこかへいくのかという死後の世界に対する恐怖が挙げられる。
死・死後への恐怖や不安は、死に面していない場合よりも死に面している場合の方がより強く感じられるだろう。しかし、岸本が、意識のある限り、まだ自分は死なないと主張をし続ける127と言っているように、死に囲まれ、それに対する恐怖や不安を持ちながらも、まだ甘い蜜を吸っていることができると思っているのが我々の姿なのであろう。
第 3 項:臨終に感じられる死
臨終は、言葉の意味から「命がまさに終わろうとする時」のことであるから128、実際に臨終の人からどのように感じているかを聞くことは不可能に近い。推測にはなるが、前項を元に考えてみると、肉体的苦痛や精神的苦痛は、死を経験している( 臨終)時であるから、苦痛は今まさに経験しているはずである。したがって、これらに対する不安や恐怖はないと考えられる。そして、次の瞬間には死後になるから、それに対する恐怖はあると考えられる。また、仏教では、臨終の時に何をどのように感じるのかということを説いているので、それを以下に述べる。
まず、仏教では臨終に三段階あると説く。「命終の位に三種有り。一に明了心通して善悪無記の心を起す。二に自体愛唯有覆無記の心を起す。三には最後不明了心唯異熟無記の心有るなり129」。そして、それぞれの位に対応して三愛( 三つの執著の心)がある。三愛とは、境界愛、自体愛、当生愛である。「行者命欲終時疾苦逼身。必起境界・自体・当生三種愛心130」。
最初の臨終は、明了心位の臨終と呼ばれ、五感を感じることができない状態である131。そのため、必死に名前を呼ばれても、体に触られても、分からないのである。しかし、この際、意識だけは朧げながらある。「命終三位の中には第六識明了心の位に… 此の位の中には初は六識を起す後には意濁り明なり132」。この臨終に入る際、境界愛が起こり、妻子や財産など自分がこの世で執著していたものと引き離されることへの苦しみを感じる。「一には境界愛、謂ゆる必死の兆現前する時、その所愛の妻子眷属屋宅などにおいて、深重の愛を生ず133」。 次の臨終は意識の臨終と言われ、意識がなくなる臨終である。「ニには自体愛の位五識已に去り細の意識濁し残て昧劣なり134」。この臨終の際、自体愛が生じ、最後拠り所としている自分の肉体から引き剥がされることに苦しみを感じるのである。「ニには自躰愛、いわゆる身心いよいよつかれ、命まさに終らんとする時、さきの所愛の妻子眷属を捨て、ただ自躰を愛し己身の命を惜しむ135」。
最後の臨終は、不明了位の臨終と言われる。「三には不明了の位六識皆去て第八識のみ残て異熟無記なり。此位を名て最後終時となす136」。この際、次に生まれたい場所への愛著が生じ、それを当生愛という。「三には当生愛、いわゆるまさしく命終る時、中有の身迎え来るを見て、すなわちその当有の生を愛する137」。
三つの臨終におけるそれぞれの愛著は、私にとっての大きな苦しみとなる。
「この三種の愛その心を流動する故に、心に愁悩を生じ命まさに尽きんとする時、風力脈を解き、千苦相い迫むが故に、身は極苦を生じ、身心苦に遇う138」。
このように、臨終にはそれぞれの段階があり、その段階ごとに我々の持つ執著の心によって苦しみが引き起こされると説かれる。また、大無量寿経では、「大命将に終らんとして悔懼交至る139」と説かれ、命が終わろうとする時、後悔と恐れが交互に現れると言われる。後悔とは自分の人生に対するものであり、恐れとは自分の行く先に対する恐れである。前項で記述した恐怖と不安は臨終において最大のものとなり、死に直面している今、残る恐怖と不安は死自体ではなく、死後に集中する。「人間にとって何よりおそろしいのは、死後の世界があるか、ないかということより、あるかないかわからない140」ことである。死の直前までは、死に対する恐怖や不安( これは死の性質に対する恐怖や不安と言い換えてもいい)があるが、死の刹那には、死を経験している以上、それらへの恐怖や不安はない。しかし、死後はまだ分からず、次の瞬間に死後に突入するため、そのことに対する恐怖や不安は極限に達しているはずである。したがって、次に問題になるのは、死後の有無であると考える。
本節では、死を客観的に分析し、それが主観にどのように現れるかを考えた。その結果、死の性質に対する不安や恐怖は死を経験するまでは感じられ、死を経験している瞬間には死後に対する不安・恐怖が最も大きくなることが分かった。次章では死後があるのかないのかを論じる。
脚注
122 ここで、生前と臨終の区別はかなり曖昧なものである。臨終とは仏教の言葉で言えば、臨命終時のことで命がまさに終わろうとする時のことである。また、本節では、死の瞬間=臨終として考える。
123 過去に死ぬような思いをしたとしても、今の感情は死を目の前にした時の感情とは違うと思われる。
124 本節では、死に対して恐怖や不安などを感じるということを前提に話を進めているが、そのように感じない人ももちろんいるだろう。その場合については、次節で言及する。
125 恐怖とは、不安が極限に達した状態のことである。恐怖まではいかない状態は不安である。ここでは、恐怖に統一して論じることにする。
126 綿貫登美子、2014、「多様化する高齢期のライフスタイルと生きがい- 高齢者の状況に配慮した就業促進と能力活用の取組み」、『千葉大学人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書』280 巻、pp.5-25
127 岸本英夫、『死を見つめる心』、pp.103-104
128 本項では、臨終とは、死ぬ瞬間、死んでいく刹那のこととする。これは死を経験している時である。
129 了慧『大経抄』( 浄全 一四・一六五上)
130 『黒谷上人語燈録』( 大正蔵 八三・一三九 a)
131 厳密には五感ではない。詳細は第 3 章に譲る。
132 義山、『大経随聞講録』(浄全 一四・四〇五上)
133 千観、『十願発心記』( 佐藤哲英、1995、『叡山浄土教の研究- 資料編- 』、百華苑、 pp.198-199)
134 義山、同書、同ページ
135 千観、同書、同ページ
136 義山、同書、同ページ
137 千観、同書、同ページ
138 同上
139 『大無量寿経』( 大正蔵 一二・二七七 a)
140 岸本英雄、『死を見つめる心』、p.28

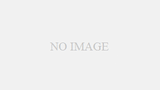
コメント