章ー節ー項
ex. 1-2-3 → 第1章の中の第2節の中の第3項
ex. 1-2 → 第1章の中の第2節
第1節:生と死の関係
第1項:人生における死とは
第2項:死をどのような観点から考えるか
第2節:死の客観的側面 ←現在地
第1項:死の人称性
第2項:死の持つ性質
第3項:人間の状況
第3節:死の主観的側面
第1項:死の主観的側面を考える際の三つの立場
第2項:生前に感じられる死
第3項:臨終に感じられる死
第4節:死から死後の問題へ
第1項:死によって人生は無意味になるか
第2項:実存哲学と仏教の死の捉え方の違い
第 1 項:死の人称性
ジャンケレヴィッチは『死』で、死には三つの人称性があるという。それは、三人称の死、二人称の死、一人称の死である。
三人称の死とは、死一般であり、「個人の立場を離れて概念的に把えられたものとしての自分自身の死」である。これは医学や生物学、統計の観点に立ち、死を記述・分析する視点である。第三人称においては、他者は自分にとって全く関係のない者であり、他者の死は目に入ったゴミの一つにしか過ぎず、せいぜい偶発的出来事にしか感じられない。
その反対に位置するのが一人称の死である。これは、私自身の死であり、他の誰にも模倣不可能な死である。第三人称が客観性を持ち、平静に考えうるとすれば、第一人称は主観的に感じるものであり、「苦悶の源泉」である。この二つは前節で述べた二つの立場にそれぞれ相応するものである。
三人称と一人称の間には、二人称の死という中間的な捉え方がある。二人称の死とは近親者の死である。他でありながら自分自身の死を最も身近に感じる死である。近親者の死を通して、死は間接的なものから直接的なものへと移行し、死が身近に感じられるようになる。
この 3 つの人称の境界を明確にすると、三人称と二人称の死は、他者に対する 私の観点であるが、一人称の死は、私に対する私の観点であり、対象と主語とが 一致する視点である。この境界は明確であり、どれだけ身近な人の死であろうが、実は私の死からは程遠い。それは、私の死を他人が経験できないのと同様に、他 人の死もまた自分が経験することはできないからである。99
本節は三人称、二人称という立場にたち、客観的に死を考える。次節では、一人称の立場から主観的な側面を考える。
第 2 項:死の持つ性質
第 2 項では、死とはどのようなものなのかを主にハイデガーをもとに分析する。客観的な死の分析は、確かにジャンケレヴィッチや岸本の指摘するように、私が主観的に感じる死とは全く異なる。だが、それは客観的に分析された死が自分の目の前に現実として訪れた時に想像以上のものとして感じられるということであり、決して死の分析が役に立たないということではない。客観的に調べられた死はあくまで学問だが、そこからしか生きている我々には死を考える術はない。故に、現実に私に差し迫ったときの死は、客観的分析の範疇を超えるということを念頭において、死の客観的分析を行う。以下の分析では、死はどのようにして我々の問題となるのか、死とはどのようなものなのかをハイデガーの『存在と時間』から考える。
ハイデガーの死の分析の結論はこうである。
現存在のおわりとしての死とは、現存在が有する、もっとも固有で、関連を欠いた、確実な、しかもそのようなものとして規定されていない、追いこすことのできない可能性である。100
ハイデガー
ハイデガーはここで、死とは「もっとも固有(代理不可能)」で、「関連を欠いた(没交渉)」、「確実な」、しかも「そのようなものとして規定されていない(未規定)」、「追いこすことのできない(追い越し不可能)」、可能性であると分析している。
a. 代理不可能性
日常の事柄に関しては、我々が「他の現存在によって代理される可能性がぞく している事情については争う余地がない」し、「代理可能性が一般に可能である」。すなわち、「~かわりに」何かをすることができる101。しかし、死ぬことは、「~ かわりに」できるものではなく、「それぞれの現存在がそのときどきにみずから じぶんで引きうけざるをえないもの」であり、「そのつど私のもの」なのである。 この意味で、死とは、私自身の最も固有なもの102である。
ハイデガーの分析によれば、私の死は、私以外の何者も経験できないものであり、何者も取って代わることができないものである103。
b. 没交渉性
死が自分に差し迫ってきた場合、「現存在にあっては、他の現存在との関連のいっさいが絶たれている」状態になる。つまり、我々が死を前にして理解するのは、死の問題を「ひたすらじぶん自身の側から引きうけなければならないということ」なのである。「もっとも固有な可能性」として死は、「単独な現存在」を要求し、そのとき、「他者たちとのあらゆる共同存在が、ものの役にもたたない」ということを我々の前に露わにするのである。104
ハイデガーが言うには、死の淵に際して、他者との交渉がなくなってしまう。死が最も固有な可能性、すなわち、自分自身(だけ)が引き受けるものであるため、他者は私の死に関して干渉することができない。死の直前までは一緒にいることはできるかもしれない。だが、「最後の瞬間はまさに道づれを許さない105」。また、無規定性とも相まって、死ぬ時期や死に方について相談をしたり、助けを要求したりすることもできない。
c. 確実性
死は確実にやってくる。我々は、日常の中で死を「たえず現前する事件として、『死亡事例』として」公共的に見知っている。しかし、「ひとは死ぬ」という事実を我々が語るとき、「逃避的に」語るのであり、それは「ひとは結局はいつかは死ぬものであるけれども、さしあたりじぶん自身にはかかわりのないことだ」という意味が含まれている。「いつかは死ぬ」という点においては、死の確実性を承認しており、「だれひとりとして疑っていない」。これは信じ込ませられたわけではなく、日々経験しているのである。しかし、あくまで「経験的に確実であるにすぎず」、「目の前にあるものではない」ため、自分の死の確実性を隠蔽しているのである。106 死が確実であり、避けられないことは、確かに誰でも知っている。我々の人生の中で何より確実なのは死だからである。だから、普通は、自分が死ぬことを真剣に考えていないが、心の底ではいつか自分も必ず死ぬことを承認しているのである。ところで、死が必ずやってくるということは避けることができないということである。我々は死の原因となる具体的原因( 例えば、ガンや事故など)は避けることができるが、死自体は避けることは絶対にできない。ゆえに、「死は、それに対していかなる態度も取り得ないがゆえにつねに暴力的である107」のである。我々に反逆は許されず、全ての抵抗は無駄に終わる。このような事実を日常生活から知っているにも関わらず、我々はその確実性を自分のこととしては考えないようにしている。パスカルはそのことを見抜き、皮肉めいて、「われわれは絶壁が見えないようにするために、何か目をさえぎるものを前方においた後、安心して絶壁のほうへ走っているのである108」と言っている。死から目を逸らすために、忙しくしたり、気晴らしをしたりするが、向かう先は変わらず、死という名の絶壁なのである。
d. 未規定性
死の持つ確実性は「<いつなのか>が規定されていない」、つまり未規定的である。すなわち、死は「あらゆる瞬間に可能であるという性格」を持つ。これも日常性から我々は分かっているが、「いずれ、いつかは」と覆い隠してしまう。「現存在は実存する」ときには、すでに「死のうちに投げこまれている」ため、実際には「あらゆる瞬間に」死はやって来る。
確実性と未規定性は一体のものであり、我々は「いつか死ぬだろうけれど、それはもっと先のことだ」と死を知らず知らずのうちに隠蔽している。しかし現実には、死はつぎの瞬間人を襲うかも知れない109。パスカルはそのことを知っていたため、「死より確実なるものはなく、死期より不確実なるものはない110」と言って遺言を書き遺している。
また、そのような人間の状況をサルトルはパスカルの有名な死刑囚の例えを持ち出し、このように書いている。
「われわれの置かれている状況は、多数の死刑囚のあいだにいる一人の死刑囚の状況と同じである。彼は、自分の処刑の日を知らないが、日ごとに自分の囚人仲間が処刑されるのを見ている」。これは必ずしも全面的にその通りだとはいえない。むしろ、毅然として処刑に対する心がまえをなし、絞首台の上で取り乱さないようにあらゆる配慮をめぐらしている一人の死刑囚が、そうこうするうちに、スペイン風邪の流行によってぽっくり連れ去られるような例に、われわれをなぞらえる方が至当であろう。111
サルトル
我々の中には、いつ来るか分からない死に対して、どうしようかと準備をする者もあれば、思考を放棄し全く考えない者もある。何をしようがしまいが、レヴィナス(Lévinas)の言うように、死が「暴力的」である以上、「いつでも不意打ちのような形で襲って」きて、我々は「取り乱して狼狽するだけ」なのである112。さらに、未規定であるということは、老若の関係がないということである。老 少不定のならいで、老いている人から死ぬわけでもなく、どれだけ若かったとしても「無常の風は時を選ばず」で、「朝には紅顔ありて、夕には白骨となれる身113」となってしまう。
もしかりに老年の死(あるいは明らさまな宣告による死)しか存在しないならば、私は、私の死を期待することができるであろう。けれども、まさに、死の特徴は、それを何時何時のこととして期待している人々を、期限以前に、つねに襲うことができるということである。114
いつやってくるかは分からないが、いつか必ずやってくる、それは次の瞬間かもしれないのである。
e. 追い越し不可能性
死の可能性は、人間存在のいわば最後の可能性であって、それを誰も追い越すことはできない。すなわち、死は現存在の極限のものであるため、その可能性を実現して経験をすることはできないということである。なぜなら、その可能性が実現してしまった時、現存在は現存在でなくなってしまうからである。「誰も死を経験したことがない」という言葉が意味するのは、まさにこの性質のことである。故に、死は我々にとって、「まったく最初の回」であり、「まったく最後の回」なのである115。
以上がハイデガーの分析である。ハイデガーの分析による死の持つ性質を改めて載せておく。
現存在のおわりとしての死とは、現存在が有する、もっとも固有で、関連を欠いた、確実な、しかもそのようなものとして規定されていない、追いこすことのできない可能性である。
ハイデガー
これらの性質を持つ死は生きている間は未だやって来ることのない「未了」のものである。これは、いつかはそれが補われて全体になるはずの不足分とは異なり、常に、一瞬一瞬、現存在に切迫しているものである116。
第 3 項:人間の状況
本項では、人間が置かれている状況を仏教で説かれている一つの譬喩を通して考える。前項で見たように、我々人間はいつ死んでもおかしくはなく、生と死は触れ合っている。死の直前までは生であり、死んだならばそれは生ではない。生と死の境は線であり、棒ではない。また、過去、現在、未来と流れる時間の流れにおいて、唯一存在するのは現在しかない。というのも、過去は過ぎ去ったものを過去といい、未来はまだ来ていないものを未来というからである。死は過去や未来には訪れないが、現在には訪れる可能性を持つ。生も過去や未来にあるのではなく、現在にしかない。過去は記憶としてあるかもしれないが、本当に過去が存在するかどうかは不確実である117。未来は訪れる可能性しかないため、これもまた不確実である。確実なのは、現在、今、この瞬間のみである。この一瞬の現在に、生も死も内包され、一息一息に生と死がおさまっているのである。これが「生死一如」と言われる所以である。生きていると言っても、常に背後には死があるのである。この人間の状況は『仏説譬喩経(義浄訳)』や『維摩経』などで「黒白二鼠の譬喩」として描かれている。ここでは『総合佛教大辞典』を参考に現代語訳をしておく118。
広野で狂象に追われた旅人は樹根にすがって空井戸に隠れる。しかし、黒白の二匹の鼠が現れ、樹根をかじり、井戸の周りを見れば蛇がシャーシャー息を吐いている。下を見ると井戸の底には毒竜が口を開けて旅人を狙っている。そんな中、旅人は上から滴る蜂蜜に心を奪われ、自分の置かれた状況を忘れている。
黒白二鼠の譬喩
これが釈迦の譬喩の内容である。旅人は、凡夫( 人間)を喩えている。狂象が喩えているのは無常である。この象は後世、絵画化される時に虎に代えられて描かれることが多かった。また、無常の怖るべきことは、無常の狼とか無常の虎と喩えられることがある。井戸は生死(苦しみ)、樹根は命、黒白二鼠は昼夜、蛇は四大、竜は死を喩えられている。最後、旅人が自分の置かれた状況すら忘れて夢中になっていた蜂蜜とは五欲のことである。無常に追われ、死が刹那に迫っているにも関わらず、その状況を忘れて快楽に身を委ねているのが我々の実相ということである。
『大無量寿経』には「世人薄俗にして共に不急の事を諍い119」と説かれ、善導はそれを
人間怱怱として衆務を営み、年命の日夜に去ることを覚えず。燈の風中にありて滅すること期し難きがごとし。忙忙たる六道に定趣無し。未だ解脱して苦海を出づることを得ず。云何が安然として驚懼せざらん。120
善導
と言っている。我々には見えないだけで恒に「死王」と隣合わせなのが人間であるのに121、急がなくてもよいことに気を取られ、自分の状況を考えようともしない。これが我々人間の姿である。 以上、本節では死が客観的にどのようなものであり、人間とどう関係があるのかを見てきた。次節では、その死が実際に我々にどのように感じられるのかという主観的な側面を考える。
脚注
99 ジャンケレヴィッチ、『死』、pp.2-36
100 ハイデガー、2013、熊野純彦訳、『存在と時間( 三)』、岩波文庫、p.170
101 但し、他者が「◯◯のかわりに死へとおもむく」ことはあり得ることであるが、これはその◯◯のかわりに犠牲になるということであり、死を取り除くことを意味はしない。( 同書、p.92)
102 これについてサルトルは、死ぬことは誰にも私に代わることのできない唯一の事柄であるというのは根拠のないものだと言っている。なぜなら、私が誰かを愛するということを考えてみると、「何びとも、私に代って愛することはできない」からである。仮にその「私の愛」を結果という観点から考察すれば、誰かが私の代わりにその人を愛するということは代理可能であるが、同様に死を結果( すなわち、教化のための死、祖国のための死) とすれば死も代理に可能になる。( サルトル、松浪信三郎、 2008、『存在と無』、ちくま学芸文庫、pp.264-267)確かにサルトルの言い分には一理あるが、ハイデガーは死が現存在にとっての最後の可能性であるということを考慮した上での最も固有なものとしたのではないだろうか。本論では、それを踏まえた上で、ハイデガーの分析をそのまま使うことにする。
103 ハイデガー、『存在と時間( 三)』、pp.90-93
104 ハイデガー、『存在と時間( 三)』、pp.135,191-192
105 ジャンケレヴィッチ、『死』、p.28
106 ハイデガー、『存在と時間( 三)』、pp.144-146、156-157、163-167、197-199
107 レヴィナス、1999、合田訳、『存在の彼方へ』、講談社学術文庫、p.138
108 パスカル、『パンセ』、p.120( 断章 183)
109 ハイデガー、『存在と時間( 三)』、pp.168-169
110 パスカル、1959、伊吹武彦・中村雄二郎・松浪信三郎訳、『パスカル全集Ⅰ 』、人文書院、p.369
111サルトル、『存在と無』、p.263
サルトルはここでパスカルの有名な囚人の例えのことを言っている。「ここに幾人かの人が鎖につながれているのを想像しよう。みな死刑を宣告されている。そのなかの何人かが毎日他の人たちの目の前で殺されていく。残った者は、自分たちの運命もその仲間たちと同じであることを悟り、悲しみと絶望とのうちに互いに顔を見合わせながら、自らの番がくるのを待っている。これが人間の状態を描いた図なのである。」( パスカル、『パンセ』、p.144( 断章 199))
112 岸本英夫、『死を見つめる心』、p.88
113 蓮如、『御文章』5 帖目 16 通(『真宗聖典』p.862)
114 サルトル、『存在と無』、p.270
115 ジャンケレヴィッチ『死』pp.338-340
116 ハイデガー、『存在と時間( 三)』、pp.97-118
117 ラッセルの世界五分前仮説はこのことを指摘している。( ラッセル、1993、竹尾治一郎、『心の分析』p.188)
118 『総合佛教大辞典』、2005、法蔵館、p.1198a
119 『大無量寿経』( 大正蔵 一二・二七四 b)
120 善導『往生礼讃偈』( 大正蔵 四七・四四〇c)
121 無常念念に至り恒に死王と居す。(『往生礼讃偈』大正蔵 四七・四四一 a)

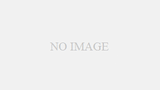
コメント