章ー節ー項
ex. 1-2-3 → 第1章の中の第2節の中の第3項
ex. 1-2 → 第1章の中の第2節
第1節:生と死の関係 ←現在地
第1項:人生における死とは
第2項:死をどのような観点から考えるか
第2節:死の客観的側面
第1項:死の人称性
第2項:死の持つ性質
第3項:人間の状況
第3節:死の主観的側面
第1項:死の主観的側面を考える際の三つの立場
第2項:生前に感じられる死
第3項:臨終に感じられる死
第4節:死から死後の問題へ
第1項:死によって人生は無意味になるか
第2項:実存哲学と仏教の死の捉え方の違い
第 1 項:人生における死とは
我々は、病気や事故で死ななくとも、必ず老い、やがては死んでいく。これに例外はない。心臓が 20 億回鼓動すれば死ぬというのは、生物学的な事実なのである83。しかし、常に老いた人を目にしているにも関わらず、実際に自分自身が老いを目の前にしないと老いたことが分からず考えられないように、死についても死の跫音を聞くまで死を考えることは幸か不幸か難しい。「幸」というのは、理屈で万人は死すという事実を知っていても、死を感じなくてよい間は事実を忘れて生きられるからである。「不幸」というのは、死を実感したときには、死について考える余裕は、時間的にも肉体的にも精神的にも残っていないからである。もちろん、観念と実感は違うため、平生健康な時と死に至る病気にかかった時とは、死を考えることは全く異なる。84
しかし、古来「生死一如」と言われるように、生を突き詰めて考えることが死を考えることにつながるのではないだろうか。観念の遊戯だとしても、死を考えることは全くの無意味にはならないであろう。
岸本は「人間が死すべきものである限り、すなわち、人間が、死という問題を抱いて生きている限り、死を忘れすぎた生活が、人間に、深い幸福をもたらすとは思われない85」という。これは岸本自身が死と対峙した時に出てきた言葉である。癌と宣告され、死が意識されたとき、岸本は「このような状況のもとにおかれて、私には、死というものを、どう考えたらよいかという問題が深刻になって きた。それをはっきりさせなければ、一刻も心を休んじていられない」86状態に なった。死を目の前にして恐れ慄き、どうしたらいいかをその時に考えていては、岸本が何のために死と向き合った闘病記を後世に残したのか分からない87。「普 段から死を思い死への心構えを怠らず、死を真剣に考え、死からの自由を貴しとし乍らも自然の必然性としてそれに服する」88ことが大事なのである。
また、サルトルは、我々は死に対して責任があるという。
人生の終わりとして死を考える限り、死は「人生の最終の現象ではあるが、やはり人生」なのであり、「人生全体に影響をおよぼす」ものである。そして、死は「私の個人的な人生の現象であり、この現象が、この人生をして、唯一の人生、すなわち、二度と繰り返すことのできない人生、決してやり直しのきかない人生たらしめるのである。したがって、私は、私の人生に対してと同様、私の死に対しても、責任ある者となる」89。ここで、責任があるというのは、「私の人生たらしめるこの有限的な性格に対して、責任がある」ということである。90
サルトル
いずれ向き合わなければならなくなる問題に、手遅れでは後悔してしまうだろう。後悔しないためにも我々は死をよく知る必要がある。
ただし、本章では死を考える際、臨死体験や蘇生は死を経験したとはみなさない。なぜなら、臨死体験や蘇生とは、「いわばこちらの世界に戻ってくるから成り立つので、『死』とはこちらに戻ってこれない事態」だからである91。確かにほとんど死んでいたのだが、「かろうじて復旧を不可能とする一撃を逃れ」たのであり92、死自体を経験したわけではないのである93。
第 2 項:死をどのような観点から考えるか
本稿では、死について、西洋哲学と仏教から考える。西洋哲学では、主に実存主義と言われる哲学者たちが実存について語るとき、そこには常に死が意識されている。実存主義の先駆けとなるキルケゴールは、「この私の生き死に」に関する哲学こそが大事だと言った。ノーベル文学賞をとったカミュは『シーシュポスの神話』の中で死という名の人生の不条理について論じている。第1章で記述したトルストイはもちろん、サルトルやハイデガーが死を扱っていることもよく知られているだろう。また、ヤスパースが哲学を始めたきっかけも「死とは一体何であるか」であった94。したがって、西洋哲学から死を論じることは妥当であろう。
また、仏教では、無常を教えられ、この世のものは全て儚く、常であるものはないと説く。全てのものは無常であるが、我々にとって一番無常なのは、命である。聖光が「八万法門は死の一字を説く95」と言っているように、仏教では常に我々の死( 無常) を問題にしてきた。古来、禅門では、「生死事大、無常迅速、各宜醒覚、慎勿放逸96」と言われてきたし、道元は『正法眼蔵』の「諸悪莫作巻」に、「生をあきらめ死をあきらむるは、仏家一大事の因縁なり97」と書き残している。死を離れた仏教はないのである。ただし、仏教では死の捉え方が、実存哲学とは異なる。それについては、本章の最後に触れることにする。
以上より、西洋哲学からも仏教哲学からも十分に死について考えることができることが分かった。次に、我々が死について扱うとき、岸本は二つの立場があるという。第一の立場は「人間一般の死の問題について」考える立場である。これは「一般的かつ観念的な」扱い方であり、客観的に死を見つめるということである。様々な人が死を分析したり、考察したりしているが、性質や学問的な記述、分析結果などは本稿では客観的なものとして扱う。もう一つの立場は「自分自身の心が、生命飢餓状態におかれている場合」の死の考え方である。これは死と向き合った時の感情であり、死への主観的な見つめ方である。これは観念的な立場とは全く異なり、「死刑囚の刑が最終的に決定するとか、神風特攻に出かけてゆく日がきまるとか、癌で手遅れを宣告される」といった「生存の見通しが絶望にならなければ」起きてこないものである98。
東西の哲学を通して、本章では、まず第 2 節で客観的に死の性質について分析を行い、続く第 3 節で、その死の持つ性質がどのように主観として現れるのかを客観的に記述する。岸本の言う第二の立場は、その状態になった人しか記述できないため、その主観的な立場を筆者が記述することは難しく、故に主観的なものを客観的に述べるにとどまる。
脚注
83 本川達雄、1992、『ゾウの時間ネズミの時間- サイズの生物学』、中公新書、p.6
84 山口哲生、1992、「『メメント・モリ』における生と死」、『活水論文集.英米文学・英語学編』第 35 号、活水女子大学、pp.43-46
85 岸本、『死を見つめる心』、p.141
86 同上、p.271
87 ユングの次の言葉も同じようなことを示唆している。「成熟し、生理的存在の頂点に達しても、目標に向かう生命の衝動は決してためらおうとしないが、中年まで上昇してきたものと同じ強さ、同じ強固さで、人生は今や下り坂となる。なぜなら、目標はもはや頂点にはなく、下降しはじめている谷にあるからなのだ。( 中略) 戦ったり、征服したりしない若者は、青春の最大の長所を逸している。そして頂上から谷へ落ちていくときに、小川の神秘に耳をかさずにいる老人は、落下の意味を理解していない。」
以上は、ユング、1973、「魂と死」『死の意味するもの』( ハーマン・ファイフェル編、大原ら訳)、岩崎学術出版社、pp.4-5
88 八代祥吉、1993、「死の問題( 最終講義)」、『キリスト教論藻』25 巻、神戸松蔭女子学院大学、p.10
89 ただし、サルトルによれば、人生がやり直せないのは我々が死ぬ存在であるからではない。我々は「他の諸可能を排除して一つの可能へ向かって自己を投企する」が、それこそ自己を有限ならしめることである。故に、死に限らず、時間が不可逆であり、私が何か行為をする以上、ふたたび始めからやりなおすことはできない。この意味において、死のうが、不死であろうが、人生は有限である。( p.295)
90 サルトル、2007、松浪信三郎訳、『存在と無:現象学的存在論の試み』、ちくま学芸文庫、pp.260-261
91 竹田青嗣、1997、『エロスの世界像』、講談社学術文庫、p.76
92 ジャンケレヴィッチ、1978、仲沢紀雄訳、『死』、みすず書房、p.373
93 もちろん、定義次第では経験したとも言えるかもしれない。ただし、本論ではそのようには考えない。
94 笠井貞、1980、「道元とヤスパースにおける「死」について- 比較哲学的研究- 」、『印度學佛教學研究』29 巻 1 号、群馬大学、pp.77-82
95 小西甚一校訂・訳、1970、「一言芳談」、『方丈記・徒然草・一言芳談集- 日本の思想5- 』、筑摩書房、p.322
96 「生死は事大なり、無常は迅速なり、おのおの宜しく醒覚すべし、慎んで放逸勿かれ」と読む。禅宗の寺で見られる「巡照板」に書かれている「無常迅速の偈」である。
97 道元、1990、水野弥穂子校注、『正法眼蔵( 二)』、岩波文庫、p.244
ここで「あきらめ」と言われているのは、「諦観」である。仏教で「諦め」とは、明らかに見るということで、その本質をありのまま見るということである。
98 岸本、『死を見つめる心』、pp.11-12

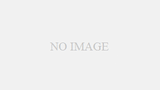
コメント