章ー節ー項
ex. 1-2-3 → 第1章の中の第2節の中の第3項
ex. 1-2→第1章の中の第2節
第1節:問いの意味
第1項:「意味」は何を意味するのか
第2項:「私」にとっての人生の意味
第3項:生きる手段と目的の違い
第2節:問いの発生過程
第1項:「問う」行為について
第2項:逆境における問いの発生
第3項:順境における問いの発生
第3節:人生の意味を問うことは有意味か
第1項:哲学的な問いとして
第2項:現代的な問いとして
第3項:普遍的な問いとして
第4節:人生の意味の必要条件
第1項:主観的かつ客観的納得
第2項:誕生肯定
第3項:絶対的な意味
第5節:幸福論 ←現在地
人生の意味は、漠然とした言葉で、幸福になることであると言われる。
すべての人は、幸福になることをさがし求めている。それには例外がない。どんな異なった方法を用いようと、みなこの目的に向かっている。( 中略) これこそすべての人間のすべての行動の動機である。首を吊ろうとする人たちまで含めて59。
パスカル
ひとが意識に目ざめた最初の時から意識が消えるまで、最も熱心に求めてやまないものは、何といってもやはり幸福の感情である60。
ヒルティ
しかも、その幸せとは他の誰でもなく自分自身の幸せである。
まず初めに人の思い浮べる人生の唯一の目的は自分一個の幸福である61。
トルストイ
しかし、実際に「私は幸福である」と言える人はどれだけあるだろうか。アランは『幸福論』の中に、不幸になることよりもむずかしいのは、幸福になることであると言っているが62、世の中は歓喜の声ではなく、愁嘆の声に満ちている。ハンナ・アーレント(Hannah Arendt)はソロン( Solon)の有名な言葉を引用し、このように言う。
「生きている間は、誰も幸福だとは言えない」という言葉の本当の意味は、「誰も幸福ではない。太陽が照らしているすべての生命に限りあるものどもは、悲惨な状況にある」ということなのである。63
ハンナ・アーレント
また、ショーペンハウアー(Schopenhauer)も断言する。
早い話が、幸福な人間は誰もいない。ただ誰もが自分の思いこんだ幸福を目指して生涯努力し続けるのであるが、それに到達することは稀である。よしまた到達するとしても、味わうのは幻滅だけである。64
ショーペンハウアー
バーナード・ショーの言う二つの悲劇を、ショーペンハウアーもまた感じ取っていたのであろうか。我々が幸福になるのはそれほど簡単ではないようである。セネカ(Seneca) もその事実を見抜き、
幸福な生を送りたいというのは人間誰しもが抱く願望だが、幸福な生をもたらしてくれるものが何かを見極めることとなると、皆、暗中模索というのが実情だ。それに、そもそも幸福な生を達成するというのは実に容易ならざる業なのであって、いったん道を誤れば、慌てて急げば急ぐほど、目指す幸福な生から遠ざかる結果を招いてしまうといったものなのだ。たどるその道が幸福な生とは逆方向に向かう道なら、急く速度そのものがますます大きな隔たりをもたらす因となるからである。それゆえ、われわれはまず自分の求めるものが何かを措定しなければならない。次には、周囲をよく見渡し、どの道をたどれば目的地に最も早く到達できるかを見て取らねばならない。65
セネカ
と忠告している。したがって、次に我々が考えなければならないのは、「その幸福がどのようなものであり、何がそれをもたらしてくれるのか」ということである。セネカの言う通り、間違った道を信じていては、どれだけ頑張っても幸せにはなれるはずがない。だが、何が間違いで、何が正しいかを見極めるのは困難を要する。なぜなら、この人生においては、「最もよく踏みならされ、最も往来の激しい道こそ、最も人を欺く道なのである66」。ゆえに大事なことは人と同じであることではなく、「理性を判断基準にする」ことである67。
さて、問題となる幸福には、どのような性質のものが考えられるか。我々が理性で考えられる幸福は次の二つに分けられるであろう。すなわち、自分の欲望を満たす、いわゆる快楽主義的な幸福68(これを一次的幸福と呼ぼう)と欲望を抑え、倫理的に行動することで得る禁欲主義的な幸福(これを二次的幸福と呼ぼう)である69。 一次的幸福は、我々が幸福と想像した時に真っ先に思いつくものである。美味しいものを食べる、お金を儲ける、他人に褒められる、好きな人と一緒に過ごす、好きな時間寝る、知識を得る、など自分が求める快楽によって得られる動物的な幸福である。ここには趣味や生きがいと言われるものも入るだろう。我々が手っ取り早く幸せを感じたければ、自分の欲求を満たせばよいのである。しかし、恐らく一次的幸福では死ぬまで満足するということがない。なぜなら、無限の欲望を有限の人生、有限の資源で満たすことは不可能だからである70。デュルケーム(Durkheim)の言葉を借りれば、まさに「無限という病」なのである71。また、快楽主義的幸福の本質をラッセルはこう言う。
道楽や趣味は、多くの場合、もしかしたら大半の場合、根本的な幸福の源ではなくて、現実からの逃避になっている。つまり、直視するには大きすぎる苦痛をさしあたり忘れるための手段になっている。72
ラッセル
また、パスカルも「気を紛らすこと73」であると言っている。欲望を満たすことによって得られる幸せに重きを置くような存在をキルケゴールは審美的実存と呼んだ74。審美的実存とは、「あれもこれも」と快楽を追求するのだが、ラッセルの言うように現実から離れてしまうため、自分を見失い虚無感に陥る。
審美的実存に絶望した人が次に求めるのが倫理的な行動によって得られる二次的幸福である。道徳的・倫理的行動とは、一言で言ってしまえば、(他人のために)善をするということである75。倫理的行動に幸せを求めるような存在をキルケゴールは倫理的実存と呼ぶ。倫理的実存とは、美的実存とは異なり、「あれかこれか」と選択することによって自己実現をし、幸福を得る。しかし、厳しく正義を追求すればするほど、理想と現実のギャップに苦しみ、絶望に陥る。 美的実存にも倫理的実存にも絶望した人が次に求めるのが宗教的実存だとして、キルケゴールは神を持ち出した。それは、カミュの言うように、「唯一の真の突破口は、まさしく、人間の判断するかぎり突破口など存在しない76」と考えたからであろう。しかし、我々は出来る限り理性に従い、神のような存在を持ち出すことは極力避けたい。なぜなら、我々が神へと向かうということは、それを不可能事だと判断したことと同じだからである。
そこで一次的幸福、二次的幸福を再度考えてみると、この両者は相対的な幸福である。すなわち、他( もしくは自己)と比べることによって初めて感じることができる幸せである77。相対的な幸せは第 4 節の条件に合わないため、人生の意味とは言えない。それとは反対に、絶対的な幸福なるものがあれば、それは人生の意味と言えるのではないだろうか。これをアリストテレスは自足的な幸福と言う。自足的な幸福とは、他に依らず、それ自体で価値がある幸福のことである。ハンナ・アーレントは、アリストテレスの幸福論について、『人間の条件』の中にこのように書いている。
幸福(eudaimonia) というのは、
ハンナ・アーレント
束の間の気分にすぎない幸せ( happiness)とも、
生涯の一定の期間には摑むことができても他の期間には失ってしまう幸運(good fortune)とも異なり、
生そのものと同じように、存在の永続的状態のことであって、変化を受けつけることもなければ、変化をもたらすこともありえないものである。78
ハンナ・アーレントのいう happiness や good fortune とは、先の一次的幸福、二次的幸福と言えるだろう。eudaimonia と言われる幸福とは明確に区別されなければならないものである。ヒルティの言葉を借りれば、前者は「不完全なもの」であり、後者は「完全なもの」である79。絶対的な幸福は、言い換えれば自足的な幸福であり、完全な幸福なのである。 ここで、アリストテレスが『ニコマコス倫理学』で eudaimonia をどのように定義しているのかを見ておく。eudaimonia とは「それだけで人生を選び取るに値するものにし、まったく欠けたところのないものにするもの」であり、「他のものと一緒に数え入れることのできないもの」である。すなわち、eudaimonia は絶対的唯一の幸福であり、それ以上何かのために求められるものではない、完全な幸福のことである80。
一次的な幸福や二次的な幸福は、それ自体のために選択されると同時に、 eudaimonia のためにも選択される。なぜなら、「私たちはそれらによって( 完全な)幸福になれると判断する」からである。つまり、一次的な幸福や二次的な幸福を求めるとき、我々はそれらが eudaimonia(完全な幸福)であると信じて求めるのであるが、実際にはそれらは eudaimonia と言われるものではないし、 eudaimonia にはなり得ない。これがアリストテレスの定義する eudaimonia である81。
この絶対的な幸福とは、具体的にどのような幸福なのであろうか。絶対的なものであるということをさらに詳しく言えば、どのような状況でも揺らぐことの ない、崩れないということであった。我々が考えうる最悪の状況とは死であろう。ということは、死を目の前にしても揺らぐことのない幸福があれば、それが絶対 的な幸福と言えるのではないか。
しかし、本当の幸福とは、いったい、何でありましょうか。人間の幸福は、複雑なものであります。いろいろの要素があって、それがいっしょになって、からみ合って、幸福がつくり出されております。しかし、人間が、ふつうに、幸福と考えているものは、傷つきやすい、みかけの幸福である場合が、多いようであります。それが本当に力強い幸福であるかどうかは、それを、死に直面した場合にたたせてみると、はっきりいたします。82
岸本英夫
岸本の言うように、それが本当の幸福かどうか分かるのは、死に直面した場合だとするならば、我々が次に考えなければならないのは、死についてであろう。次章は、死を手がかりに人生の意味について考える。
脚注
59 パスカル、『パンセ』、p.260( 断章 425)
60 ヒルティ、1978、草間平作訳、『幸福論( 第 1 部)』、岩波文庫、p.206
61 トルストイ、1997、中村融訳、『人生論』、岩波文庫、p.42
同書 p.37 には「人は誰しも生きる以上、ひたすら自分のために善かれと思い、自分の幸せを願っている。人が自分に幸せを望む気持を感じないとしたら、それは自分を生きているものと感じていないことだ。人は自分への幸福をねがう気持ぬきにしては、人生を想像することはできない。誰にとっても生きるということは、幸せを望み、それを得ようとすることにほかならない。」と書いている。
62 アラン、1998、神谷幹夫訳、『幸福論』、岩波文庫、pp.311-312
63 ハンナ・アーレント、1994、佐藤和夫訳、『精神の生活( 上)』、岩波書店、p.191
64 ショーペンハウアー、2011、斎藤信治訳、「現存在の虚無性に関する教説によせる補遺」、『自殺について 他四篇』、岩波文庫、p.36
65 セネカ、『生の短さについて』、pp.133-134
66 同上
67 同上
68 エピクロスは快楽主義の筆頭としてよく挙げられるが、エピクロスの快楽主義はここでいう快楽主義とは別物である。
69 なぜここで道徳的・倫理的行動が禁欲主義的な行動となるのかというと、我々は本質的には欲望でしか動かない生き物だからである。したがって道徳や倫理を守ろうとすると必ず何かしら欲求を抑えることになる。
70 不可能ではあるものの、経済学が追求するのは有限な時間・資源の中でいかに無限の欲望を満たすことかであり、多くの人が一時的であれ幸せを感じるためには大切なことである。
71 「欲求の肥大化」「欲望の無限化」とも言い、社会学の観点から論じている。
72 ラッセル、『幸福論』、p.179
73 パスカル『パンセ』、pp.112-113( 断章 165 の 2)
74 また、無関心な知的立場も審美的実存に入り、キルケゴールはヘーゲル主義をそのように位置づけている。( 山下秀智、『宗教的実存の展開』、p.54)
75 あえて「他人のために」と書いたのは、「自分のために」と欲望から善をする者もいるからである。
76 カミュ、『シーシュポスの神話』、p.63、「ある注釈者はシェストフのつぎのような言葉を伝えているが、この言葉は注目に値する。『唯一の真の突破口は、まさしく、人間の判断するかぎり突破口など存在しない所にある。そうでなければ、どうしてわれわれは神を必要としよう。ひとが神へと向うのは、ただ、不可能事を獲得したいためにほかならない。可能事についてなら、人間でこと足りる。』」
77 もし比較対象がなければ、それは絶対的なものとなるため、その幸せが揺らぐことはない。得た幸せが揺らぐということは絶対的ではなく、相対的なのである。
78 ハンナ・アーレント、『人間の条件』第五章「活動」を森一郎が訳したもの。( 森一郎、1998、「哲学にとって死はどこまで問題か」、『東京女子大学紀要論集』、49 巻 1 号、p.18
79 ヒルティ、『幸福論』第 3 部、岩波文庫、p.10
80 アリストテレス、2014、神崎繁訳、「ニコマコス倫理学」、『アリストテレス全集15』、岩波書店、pp.18-61
81 ただし、アリストテレスが『ニコマコス倫理学』で eudaimonia として考えているものは「いかに生きるか」の範疇のものであり、言葉の由来も「善き活動」と結びつく表現であるため、日本語の幸福とはズレがあるのだが、さしあたり本節では概念だけを借り、アリストテレスが何を意図していたかまでは触れない。
82 岸本、『死を見つめる心』、p.40

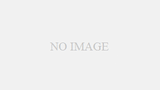
コメント