章ー節ー項
ex. 1-2-3 → 第1章の中の第2節の中の第3項
ex. 1-2→第1章の中の第2節
第1節:問いの意味
第1項:「意味」は何を意味するのか
第2項:「私」にとっての人生の意味
第3項:生きる手段と目的の違い
第2節:問いの発生過程
第1項:「問う」行為について
第2項:逆境における問いの発生
第3項:順境における問いの発生
第3節:人生の意味を問うことは有意味か
第1項:哲学的な問いとして
第2項:現代的な問いとして
第3項:普遍的な問いとして
第4節:人生の意味の必要条件 ←現在地
第1項:主観的かつ客観的納得
第2項:誕生肯定
第3項:絶対的な意味
第5節:幸福論
本節では、どういうものであれば、「私が人間に生まれ、生きていく究極の目的は何か」という定義の人生の意味であると言えるのか考える。人生の意味に関する書物、先行研究を元に、大きく三つの角度から必要条件について論じる。
第 1 項:主観的かつ客観的納得
人生の意味と言えるものの必要条件の第一として、「主観的かつ客観的に納得できる」ということをあげたい。主観的な納得とは、自分自身が「これが人生の意味だ」と納得でき、しかもそれが揺らがないということである。客観的な納得とは、客観的に見て「それが人生の意味だ」と納得できるようなものということである。この二つの視点を端的に言えば、主観的な自己の視点とは、感情であり、客観的な自己の視点とは、論理であり哲学的思考である。
分析哲学において、人生の意味に関する哲学的議論をまとめたメッツ( Metz)は、人生の意味を考える立場として、「超自然主義」、「主観主義」、「客観主義」の 3 つに分類している44。「超自然主義」とは、人生の意味をスピリチュアルな領域と関連させる立場である。本論では、この立場は取らないので詳細は省く。次に、「主観主義」とは、人生を意味あるものにするのは主観であるという立場である。メッツは主観主義の最大の問題点として、「本人がそれに満足していたらたとえどんな内容の人生であったとしても意味があることになる」という点を見ている45。すなわち、主観主義の立場をとるならば、例えばヒトラー(Hitler)やスターリン(Stalin)の人生は肯定される可能性がある。彼らは数え切れないほどの命を奪い、人を支配していた。それが彼らにとっての使命であり、それを人生の意味として考えていたのであろう。とするならば、主観的にはその人生で満足しているため、他人がどうこう言おうが関係なく、ヒトラーやスターリンの人生には大きな意味があったのである。
しかし、これは感情的に納得できない。したがって、メッツは、「他人に害を与えるだけの人生や、ただ生きているだけの人生にたいした意味はないだろう」と言い、人生の意味は他人や社会に善をもたらすようなものに客観的に決まるであろうと言うのである46。そして、メッツはマンデラ(Mandela)やマザー・テレサは善という点で、ダーウィン(Darwin)、アインシュタインは基盤的真実を発見した点で、ドストエフスキー、ピカソ(Picasso)は美という点で、客観的に有意味であると主張する47。
確かにメッツは一見正しいことを言っているように見えるが、森岡の言うように「人生の意味」が意味する内容を捉え損ねている48。つまり、どれだけ客観的に見て、人生の意味があるように思えたとしても、「人生の意味」が私の人生の意味である限り、当の本人がそれを人生の意味と感じなければ、その人にとっての人生の意味にはならないのではないだろうか。これは第 1 章の第 2 項で述べた通り、外から社会的な価値の有無は言えるが、人生の意味の有無は言えないということである。もし客観主義の立場にたったならば、この世には人生に意味がある人とない人が存在し、社会的に価値がない人は人生の意味がないというような暴論に発展する恐れがある。
主観主義の立場にたっても、客観主義の立場にたっても、上手くいかないのはなぜか。それは主観と客観を分離しているからである。本来、主観・客観の二つの視点は我々にどちらも備わっている視点である。例えば、ネーゲル(Negel)が例を挙げるように、「はるか外側からみれば、自分の誕生は偶然で、人生は無意味で、自分の死はとるに足らないように思える」一方で、「内側からみれば、自分が生まれなかったなんて想像することすら不可能に近いし、自分の人生はとてつもなく重要で、その死は悲劇的に思える」のである。我々は内部の観点(主観)からも外部の観点( 客観)からもどちらからも逃れることはできない。しかもこの二つの観点のどちらかに一貫した態度をとって人生の意味や目的を考えることはできないのである49。
第 2 節や第 3 節で述べたように、我々が人生の逆境に遭遇したとき、我々は 人生の意味について深刻に考えることがある。しかし、これは感情的なもので一 過性のものと考えられる場合もあり、事態が変化することで考えなくなること もあるだろう。一方、哲学的な問題としての人生の意味は、客観的に乖離するこ とから起こるため、「主観的に完璧であっても客観的な無意味さで人生を脅かし、真剣に生きていたとしても、不条理によって脅かしてくる50」ものである。主観 的な視点は、哲学的に人生の意味が問われた時、「整合性を保ちつつ内側から正 当化することはできない」だけでなく、正当化を見つけることすらできない。故 に、我々が人生の意味を考えるときに主観的な視点からだけ満足できるもので は不足となる。逆に、客観的な視点からだけ満足できる場合は、「私」という主 体が忘れ去られている場合がある。人生の意味とはそもそも「私」の人生の意味 であるから、主体を欠いては本末転倒である。 したがって、主観と客観、双方の納得が人生の意味といえる為の第一必要条件として挙げられる。カミュの言葉を借りれば、「本質的な問題」(ときにひとを死なしめるかもしれぬ問題、あるいは生きる情熱を十倍にする問題51)に答える思考法は、「ラ・パリス的な思考方法」(自明性)と「ドン・キホーテ的な思考方法」(叙情的態度)しかなく、この二つの均衡によってのみ、我々は「感動と明晰に同時に到ることができる」のである52。
第 2 項:誕生肯定
人生の意味の必要条件の第二として考えたいのは、それによって人生を後悔しないものにし、生まれてきたことを肯定できるという条件である。これについて、森岡正博の「悔いなく生き切る」ための生命学を元に考える53。森岡によれば、「悔いなく生き切る」とは三つの側面からとらえられる。
まず、生まれてきたこと自体を肯定できるという側面である。もし、「生まれてこなければよかった」という考えになってしまえば、それは生まれてきたことへの後悔であり、しいては人生を否定・後悔することである54。したがって、誕生を肯定できなければならない。
この「生まれてきて本当によかった」というのは「生きていてよかった」という言葉とは似て非なるものである。「生きていてよかった」とは、裏に隠れているのは「今まで死なないでよかった」という意味である。しかし、「生まれてきて本当によかった」とは、「この世に生をうけたことそれ自体が、本当によかった」という誕生を肯定することなのである。 「生まれてきてよかった」という誕生を肯定できると同時に、今まで生きてきた人生そのものを肯定できなければ、悔いが出てきてしまう。すなわち、その時々は、悔いのある人生なのであるが、死に面したときに、その悔いのあった瞬間も含めた人生を丸ごと肯定できるのが「悔いなく生き切る」ということである。
さらに、悔いがないのはまさにこの人生であるから、「別の人生のほうがよかった」という考え方にはならない。つまり、「もっとこのようにしたかった」という欲望やその側面から、「こんな人生は嫌だ」という絶望のないことが「悔いなく生き切る」ということである。
森岡はこの三側面から「悔いなく生き切る」ことを定義している55。この「悔いなく生き切る」ことはキルケゴールの「私がそのために生き死にできる」と言ったことに近いと思われる。そのことを踏まえて、まとめると、人生の意味とは、
「私が生まれてきたのはそのためであり、そのために今まで生きてきた」と言えるものであり、それを実現できたならば56「本当に生まれてきてよかった。このために生まれてきて、今まで生きてきた。これから生きていても満足だし、いつ死んだとしても後悔することはない」と言えるものである必要がある。
第 3 項:絶対的意味
第三番目の必要条件は、絶対的な意味である。仮に、相対的なものであるとすれば、意味がなくなってしまう場合があるということになってしまうからである。人生の意味は、どんなことがあっても、どのような状況でも決して揺るがない、絶対的な意味であるべきではないかどうかを考えてみる。
人生の意味が絶対的であるならば、第 2 項の誕生肯定も絶対的な肯定になる。そこで、人生が絶対的な肯定されない場合を考えてみると、人生が相対的には良いにも悪いにもなる、もしくは人生が絶対的に否定されるという場合が考えられる。また、誕生肯定が絶対的なものであれば、その人生の意味においては、自殺は完全否定される57。反対に、誕生肯定が相対的なものであるとすれば、自殺は肯定されうる。自殺が肯定されうる場合について、さらに分析してみると、
A.死が最善の状態である。(Being dead is the best state possible.)
B.生が最悪の状態である。(Being alive is the worst state possible.)
C.死が生よりも善い状態である。(Being dead is better than being alive.)
C1.死が常に生よりも善い状態である。(Being dead is always better than being alive.)
C2.死が時として生よりも善い状態である。(Being dead is sometimes but not always better than being alive.) 58
という場合が考えられる。人生はこの 4 つの場合と「生が最善の状態である」、すなわち、生は絶対的な意味を持つという計 5 つの場合しか考えられない。これ は、相対的な次元で生の方がいいという理由は自殺を止める理由にはなり得ず、むしろ自殺を合理的にしてしまうということを示している。すなわち、絶対的な理由がなければ、死を選ぶことは悪くないということになってしまうのである。逆に言えば、人生の意味が絶対的なものであれば、それは生を絶対的なものにし、自殺が合理的に完全に否定されるということである。我々が生きる理由を探求し、死んでもいい理由を否定する以上、人生は絶対的な意味を持たなければならなくなる。
絶対的とは、また、完成ということでもある。完成とは、もうこれ以上変化しない、不変のものということである。変化してしまえば、その前後で比較でき、それは相対的なものとなってしまう。故に、変化があるならば相対的なものであり、絶対的なものならば不変であり、完成したものである。
以上の三つの人生の意味の必要条件をまとめると、
この三つの条件が「これが人生の意味である」というための最低必要な条件とした上で、本論では人生の意味について考えていく。
脚注
44 メッツはまず大きく超自然主義と自然主義の二つの立場に分け、自然主義をさらに主観主義と客観主義に分けている。超自然主義とは、人生の意味をスピリチュアルな領域と結びつけて考える見解であり、自然主義は科学的な方法によって人生は有意味になると考える見解である。
45 森岡正博、2015、「『人生の意味』は客観的か: T・メッツの所説をめぐって 生命の哲学の構築に向けて( 7)」、『現代生命哲学研究』、大阪府立大学 21 世紀科学研究機構現代生命哲学研究所、p.84
46 同上、pp.84-85
47 真・善・美を兼ね備えた人生こそが客観的に意味を持つ人生であるという主張である。
48 同上、pp.87-90
49 トマス・ネーゲル、2009、中村昇( 他) 訳、『どこからでもない眺め』、春秋社、 pp.341-344
50 ネーゲル、『どこからでもない眺め』、pp.350-357
51 ここで、カミュが本質的な問題と言っているのは、人生の意義のことである。人生の意義( =人生の意味) は無いと分かるや人を死なしめ、あると分かれば生きる情熱を何十倍にも膨れ上げさせるものであるため、このように言っているのであろう。
52 カミュ、『シーシュポスの神話』、p.13
53 ただし、森岡は、生命学は人生論などとは異なり、一般的な人生の意味や目的に答えを与えるものではなく、それらは一人一人が責任を持ち答えなければならないとしている。
54 例えば、デイヴィッド・ベネター( David Benatar)は Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence. ( 2006) の中で、全ての人間は生れてこなかったほうがより良かったということを論じているが、そのような考えは「悔いなく生き切る」ことの弊害となる。また、そのことについては、森岡( 2012) がベネターの議論の誤謬を指摘している。
55 以上は、下記の文献を参照。
森岡正博、2007、「生命学とは何か」、『現代文明学研究』第 8 号、pp.447-486
森岡正博、2011、「誕生肯定とは何か: 生命の哲学の構築に向けて( 3)」、『人間科学』第 6 号、pp.173-212
森岡正博、2012、「『生まれてこなければよかった』の意味: 生命の哲学の構築に向けて( 5)」、『人間科学』第 8 号、pp.87-105
森岡正博、2013、「『生まれてくること』は望ましいのか: デイヴィッド・ベネターの『生まれてこなければよかった』について」、The Review of Life Studies、第 3号、pp.1-956 ここでは、人生の意味が実現できるものという前提で語っているが、そもそも実現できるものなのかどうかなどの議論は後述する。
57 人生の意味は「生きる意味」であるから、「死んでもいい( 自殺が可能な) 意味」があっては困る。自殺は、生きることもできるのに死を自ら選ぶという点において、他の死よりも特徴的である。
58 James. Warren、2001、Socratic Suicide、The Journal of Hellenic Studies 、Vol.121、pp.91-92

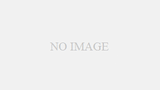
コメント