章ー節ー項
ex. 1-2-3 → 第1章の中の第2節の中の第3項
ex. 1-2→第1章の中の第2節
第1節:問いの意味
第1項:「意味」は何を意味するのか
第2項:「私」にとっての人生の意味
第3項:生きる手段と目的の違い
第2節:問いの発生過程
第1項:「問う」行為について
第2項:逆境における問いの発生
第3項:順境における問いの発生
第3節:人生の意味を問うことは有意味か ←現在地
第1項:哲学的な問いとして
第2項:現代的な問いとして
第3項:普遍的な問いとして
第4節:人生の意味の必要条件
第1項:主観的かつ客観的納得
第2項:誕生肯定
第3項:絶対的な意味
第5節:幸福論
本節では、哲学的な側面、現代的な側面、普遍的な側面の三側面から如何に人生の意味を本論で扱うことに意味があるのかを考える38。
第 1 項:哲学的な問いとして
古来、哲学の永遠のテーマは「生きるとは何か」、「生きる意味とは何か」であ った。ソクラテス( Socrates)、アリストテレス( Aristotle)から始まり、現代 では、実存哲学者と言われるキェルケゴール、ヤスパース( Jaspers)、ハイデッ ガー( Heidegger)、サルトル( Sartre)、は私たちの存在について哲学的に分析 している。また、文学の世界では、ドストエフスキー( Dostoevsky)、カミュ( Camus)は文学作品を通して、この悩ましい人生の意味について私たちに問いかけてい る。精神科医、心理学者の分野ではフランクルが実存の意味を研究している。なぜ、それほどまでに取り憑かれるテーマなのか。それはトルストイのこの言葉に凝縮されているだろう。
この疑問は実に愚劣な、単純な、子供臭いものに思われていたのだが、いざ取り上げて、解決しようという段になると、たちまち私は、まず第一に、それが子供じみた愚かしい疑問でなどないどころか、人生における最も重大にして深刻な問題である39
この重大な問題は、西洋だけでなく、東洋でも古くから重要視されていた。その一つとして有名なのは釈迦の出城入山の話である。
釈迦は子供の頃、シッダルタ太子と呼ばれ、王家に生まれ、何不自由なく暮らせる環境で育った。類まれなる学才と秀でた武芸の才能も持ち、文武において比肩する者はいなかった。しかし、何においても恵まれていた太子は、過保護な親のせいか、病人や死者を見たことがなかった。あるときは、カピラ城の東門から外に出て、初めて老人を見て、老いる苦しみを知る。あるときは、南門から出て、病人を見て、驚き、病の苦しみを知る。そしてあるときは、西門から出て、死人を目撃し、驚歎して、死ぬ苦しみを学ぶ。最後は北門から出て、出家した修行僧を見て、感動した。これが釈迦の四門出遊である。この出来事以降、太子は時折、何か物憂げな表情をし、それを心配した父王はインド一の美女ヤショダラを妻として娶り、さらには多くの美女を住まわせた四季の御殿まで造ってしまう。しかし、釈迦の悩みは物質的なものではなく、精神的なものであった。ある晩、城で寝ようとした時に、昼間は華麗な美女が、目の前で醜い姿を晒して寝ているのを見て、太子は城を出た。王は出家しようとする太子を引き留めようと望むものを聞くが、太子は三つの苦しみ( 老苦、病苦、死苦)をなくすことが望みという。しかし、老苦、病苦、死苦をどうしてなくすことができようか。すべてを動かす権力を持ち、何でも揃えることができる金を持っていたとしても、これだけはどうしようもなかった。なぜこれだけの苦しみがあるのに生きなければならないのか、太子の疑問は誤魔化すことができず、ついに出家修行の身となった。
以上が釈迦出家の顛末である。苦が満ち溢れている人生を何のために生きるのかが仏教の原点であったのである。 古今東西、哲学の大きな関心は人生の意味であったことが以上より分かるであろう。しかも、それは一般的な問題というより、個人の心の奥底から出てくる問いなのである。
第 2 項:現代的な問いとして
人生の意味に悩む人は決して哲学者だけではない。言葉や表現は違えども、人生の意味は考えられているのではないだろうか。「人生は苦なり」の釈迦の言葉に例外なく、予期せぬ天災、人災に悲鳴をあげ、苦しみ悩む人は多い。豊かさが幸福につながると信じて、戦後の日本は進歩、発展してきた。GDP の推移を見れば、いかに努力してきたかが分かるであろう。日本に限らず、世界中のすべての国・人は豊かさを求めて努力していることに疑いはない。
しかし、この豊かさは幸福につながり、苦悩は減っただろうか。科学・医学は日進月歩で、宇宙開発や遺伝子解析、スマートフォン、3D 映像、一昔前には夢と思われていたことが数年で実現してしまう世界となった。そんな世界において、自殺者が無くなったという報告もなければ、人生は苦しくないと言い切る人すらもない。どれだけ金を持っている人であっても、どれだけ豊かな生活をしている人であっても、苦しんでいることに変わりがない。この不足の時代が終わった今になって、我々は豊かさと幸福がつながらず、豊かになるために生きているのではないということが分かってきたのである。
モノが溢れかえっているこの時代で、増えてきていると言われているのが実存的空虚に悩む人々である。実存的空虚とは、フランクルの言葉で、人間の実存に悩み、心が空虚感で満たされる人々が増えてきているというのである。
私たちは今日ではもはや、フロイトの時代におけるように性的な欲求不満と対決しているわけではなくて、実存的な欲求不満と対決しています。また今日の典型的な患者は、もはやアドラーの時代におけるように劣等感にさほど悩んでいるわけではなく、底知れない無意味感に悩んでおり、そしてこれは空虚感と結び合わされているので、私は実存的真空と呼んでいるのであります。40
フランクル
具体的に言うと、何をやっても満たされない、何だか虚しい、何かが足りないわけではないけど「何か」が足りない、不幸ではないがとりわけ幸福というわけでもない、といった悩みである。諸富は、次のように、このことをうまく言い表している。
今、「どこまでも、透明な絶望」とでもいうべきものにとらわれていることにあるように私には思える。
諸富祥彦
それは、今は暗黒の闇の中にいるけれども、そこから脱出できれば明るい未来が見えてくる、といった類の絶望ではない。
人生の深い、谷間に沈んでいる。そのような絶望ではない。それはむしろ、どこまでいっても同じことがくり返されていくだけの、透明な絶望。深い闇ではないが、どこまでもまっ平らな未来の、先の先まで透けて見えていて、そこから抜け出すことなど永遠に不可能に思える、そんな絶望。
ただ今と同じ日常だけがどこまでもくり返されていく。そんな現代日本社会は、言うまでもなく、ナチスの強制収容所に比べればとんでもないほど豊かで、平和な社会である。41
これは『完全自殺マニュアル』で述べられている自殺の要因に共通している。
あなたの人生はたぶん、地元の小・中学校に行って、塾に通いつつ受験勉強をしてそれなりの高校や大学に入って、4 年間ブラブラ遊んだあとどこかの会社に入社して、男なら 20 代後半で結婚して翌年に子供をつくって、何回か異動や昇進をしてせいぜい部長クラスまで出世して、60 歳で定年退職して、その後 10 年か 20 年趣味を生かした生活を送って、死ぬ。どうせこの程度のものだ。42
『完全自殺マニュアル』より
自分の人生が他人と同じような人生に見え、「ひとりひとりが無力で、いてもいなくてもどうでもいい存在」に思われる。そして、変わり映えのしない毎日が 「延々と同じように続いていく」と感じる。あまりに未来が透明であるがゆえに、そこに何の意味があるのか分からなくなる。これをフランクルは実存的空虚と 呼んだのである。日本では諸富の調査により、このような空虚感を持つ人が現代に多いということが分かっている43。
人生の意味とは、「そのような人生」の意味であるから、これさえ分かれば実存的空虚は霧散するであろう。したがって、人生の意味を本論で探求することは現代人にとって大きな価値があると考えられるのである。
第 3 項:普遍的な問いとして
人生の意味は、考えたことがある人だけでなく、考えたことがない人にとっても大事な問いであり、現代だけでなく、どの時代においても大切な問いである。すなわち、人生の意味は老若男女、貴賤を問わず、すべての人にとって知っておくべきことであると考えられる。どれだけ自分と人生の意味を考えることとは関係がないと思っている人であっても、前節で述べた通り、将来考える時が来るかもしれないからである。順境の時でも問いが発生する可能性がある以上、どのような人でも問いが発生する可能性はあるのである。また、人生の意味を考えるということは、自分の未来の目的を考えるということであるから、積極的に肯定されることはあっても、否定されることはないように思われる。
このような意味で、人生の意味は一個人の問題であると同時に、普遍的な問題でもある。 本節で、人生の意味を考えることは学問的にも、社会的にも価値があり、それはどのような人にとっても知っておいて損はないということが分かった。
脚注
38 浦田は、「永遠の問いとして」、「現代的な問いとして」、「学問上の問いとして」と分けて論じている。永遠の問いとしての人生の意味は、本節では普遍的な側面にあたり、学問上の問いとしては哲学的な側面にあたる。浦田は「永遠の問いとして」の中で主に時間的な観点から、昔から今まで問われ続けている人生の意味という問いを示した( 浦田、2013)。しかし、本節における普遍的な側面とは、時間だけでなく空間的にも、すなわち過去から現在、未来にわたる全ての人が問うべき、考えるべき重要な問いとしての人生の意味の側面である。
39 トルストイ、『懺悔』、p24
40 フランクル、『生きがい喪失の悩み』、p.14
41 フランクル、『生きがい喪失の悩み』、pp.203-204(諸富祥彦の解説)
42 鶴見済、2008、『完全自殺マニュアル』、太田出版、p.7
43 諸富祥彦、1999、『むなしさの心理学』、講談社現代新書

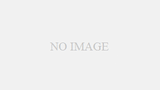
コメント