章ー節ー項
ex. 1-2-3 → 第1章の中の第2節の中の第3項
ex. 1-2→第1章の中の第2節
第1節:問いの意味
第1項:「意味」は何を意味するのか
第2項:「私」にとっての人生の意味
第3項:生きる手段と目的の違い
第2節:問いの発生過程 ←現在地
第1項:「問う」行為について
第2項:逆境における問いの発生
第3項:順境における問いの発生
第3節:人生の意味を問うことは有意味か
第1項:哲学的な問いとして
第2項:現代的な問いとして
第3項:普遍的な問いとして
第4節:人生の意味の必要条件
第1項:主観的かつ客観的納得
第2項:誕生肯定
第3項:絶対的な意味
第5節:幸福論
1-1で本論で扱う「人生の意味」の定義を定めたが、そもそもこれを我々人間が問うことがなければ、考える必要はない。本節では、まず「人生の意味」とはどういう問いなのか(1-2-1)に始まり、その問いがどういう時に起こり得るのか(1-2-2、1-2-3)を考える。
第 1 項:「問う」行為について
「人生の意味は何か」は、一種の問いである。もちろん、他の問いの内容とは一線を画するが、問いの構造は同じである。すなわち、私たちが問うということは、「なぜ」「何のために」と理由・意味を聞くことである。松井は、意味を問うことが他の一般動物とは異なる人間の本質であると主張する27。意味を問う中でも、存在への問いは他種には決して生まれないだろう。イーグルトン( Eagleton)は、ハイデガー( Heidegger)の言葉を借りて、他の動物とは異なり、「人間は単に存在することにその特徴があるのではなく、そのような存在が問題となる」ところに特徴がある。他の動物が心を悩ませるのは捕食動物から逃れることや子育てであろうが、人間は自らの状況に対峙し、「存在論的不安」に頭を悩ませるのであると述べている28。パスカルが「人間は考える葦である」といい、「われわれの尊厳のすべては、考えることのなかにある」と言った29のは、単に考えることにではなく、存在について考えることについて言ったのではないだろうか30。問うという行為、中でも存在について問う、これが我々人間と他の動物との決定的な相違点なのである。
シェイクスピア(Shakespeare)は『ハムレット』で「食って寝るだけに生涯のほとんどをついやすとしたら人間とはなんだ? 畜生と変わりがないではないか。」と言わせている31。「食って寝るだけ」とは、文字通りの意味ではなく、前節の言葉を借りれば「どうやって生きていくか」という生きる手段のことであろう。確かに生きるための手段ならば、高い知能を持つ動物であれば考えている可能性はあるだろう。だからそれだけに人生をかけているならば、それは畜生と変わりはない。
問うという行為、中でも存在への問いは人間特有のものだと分かった。では、この存在に関する問いはどのようにして発せられるのであろうか。以下、二つの場合に分けて、問いが発生する過程を考える32。これはそのまま、この議論の対象者を意味する。
第 2 項:逆境における問いの発生
我々が逆境(苦しい時や辛い時)に立たされた場合、しかもそれが極めて重大な場合、人生の意味を問うことがあると考えられる。我々は何か未来に目的を持って生きているが、その目指している目的が困難により達成不可能となったとき、「一体、私は今まで何のために生きてきたのだろうか」「こんなに苦しいのになぜ生きていなければならないのか」と問うのである。それは、それまでその目的によって人生が意味づけられてきたため、目前の目的が達成されないことにより、過去の一連の行為の意味を持たないように感じてしまうからである33。
分かりやすい例として、フランクルが強制収容所での体験を心理学的に分析した『夜と霧』の内容から考えてみる。フランクルによれば、被収容者には二タイプの人間がいた。すなわち、苦しさに耐えきれなくなって自殺を図った人と、苦しさに耐えて解放まで生き延びた人である。この違いをフランクルは自分の生きる意味を見出していたかどうかで分けている。家族を失い、一向に解放の希望がない中で、頑張り抜く意味を見失った人は励ましも慰みも拒み、「生きていることにもうなんにも期待がもてない」と言葉にし、崩れていった。自分の家族がまだ待っている、自分の研究はまだ終わっていないと、未来に希望を持っていた人は、いかなる苦しみも耐え抜いたと言う。耐え抜いた人たちの中でも、解放後に自らの家がなくなり、家族もいないことを知った途端に絶望の淵に立たされた人もいる34。 このように自分が目的としていたものが逆境によって、達成が不可能になると我々は人生の意味を問わずにはいられなくなる。故に、どんな逆境によっても崩れない目的である必要があるだろう。このことについては第 4 節で詳述する。
第 3 項:順境における問いの発生
逆境において人生の意味の問いが発生するのは想像しやすいが、順境の時に も発生する可能性が考えられる。例えば、人生が上手くいっているにも関わらず、
「この人生に何の意味があるのだろうか」と問う可能性があることは考えられる。そのような問いは進行形で上手くいっている時よりも、当面の目標が達成された時に発生すると思われる。ノーベル文学賞を授与され、英語圏の国々で多大な功績を残した才人であるバーナード・ショー( Bernard Shaw)が、“ There are two tragedies in life. One is not to get your heart’ s desire. The other is to get it.” と言っているように、我々は夢を叶えた時でさえも悲劇になりうる35。どうしてそのようになってしまうのだろうか。
逆境の場合は、それまで意味を与えていた目的( ここで使っている目的とは最終項ではなく、通過点という意味での目的であり、目標と同義)の喪失により、それまでの人生が無意味に思われるのであった。それに対して、目的を達成した場合は、それまでの一連の行動の意味が確定する。目的達成は同時に目的の喪失にもなり、その時、このような問いが浮上してくる。「私はこれまでうまくやってきた。これから何を目指せばいいのだろう。そもそも私は最終的に何を目指しているのだろう。」という問いである。この場合は、逆境と異なり、未来の行為の意味付けが不明なため、人生全体の意味に関する問いが喚起される36。
先述したトルストイも順境において人生の意味の問いを考えた一人であったが、功利主義で有名なミル( Mill)もそうであった。ミルはそのことを「精神の一大危機」と題し、『ミル自伝』の中に書き記している。 幼少期から父の熱心な英才教育を受けたミルは、教養はもちろん、考える力を身につけ、「同世代に二十年ほども先んじて」いるくらいの知識を修得していた。 1821 年、ミル 14 歳の冬、初めてベンサムを読み、それ以来、「生涯の目的と言えるものとして、世界の改革者になるという大志を抱くようになった」。これは、ミルにとって「永遠に価値のあるもの」であり、「本当の生き甲斐」であったのだが、1826 年 20 歳になった彼は突然、「ぼんやりと無感覚な状態に陥って」しまう。喜びにも刺激にも反応せず、楽しいという感覚のないそんな時にふと「生涯の目的がすべて実現したら、今めざしている制度や思想の改革が今この瞬間にあますところなく実現したら、おまえは本当にうれしいのか。本当に幸福なのか」という声なき声が聞こえてくる。それに対し、「私の中の私は、抗いがたい率直さで『否』と答えた」という。今までの世界の改革者になるという目的を追求するために生きてきたミルは、その拠り所が崩れ落ち、「もう生きるに値するものは何もない」と思うにまで至った。当時の心境をコールリッジの詩を引用して書き表している。
虚ろで暗くおぞましく、疼きも覚えぬこの苦しみ、
J.S.ミル
精気を奪い、息を詰まらせ、感情すら失わせるこの悲しみ、
言葉に、溜息に、涙に逃れたい
だが願いはむなしく、憂いは晴れない
そんな憂鬱な状態に居ても立ってもいられず、愛読書や過去の賢人・偉人が残した書物を手当たり次第に読み漁った。しかし、努力虚しく、いつもは元気づけてくれるこれらの書物も「あのときは沈黙していた」という。37
トルストイもミルも順風満帆な人生を歩んでいたはずなのに、ふと人生について思いを馳せた途端に、人生の意味の問いに悩まされたのである。これは決して挫折したからではない。いかに人生が順境で、何事もなく上手くいっていたとしても、このように人生の意味に悩まされることはあるのである。
本節では、「何のために生きるのか」という存在の問いは、人生のいかなる場合にも問われる可能性があることが分かった。では、その問いはどれくらい重要なものなのか、また実際に問われているのかを次節で考える。
脚注
27 松井春満、2000、「人間が生きるということ- 教育人間学の視点から」、『総合研究所所報』第 8 号、奈良大学総合研究所、pp.19-20
28 T.イーグルトン、2013、有泉学宙・高橋公雄・清水英之・松村美佐子訳、『人生の意味とは何か』、彩流社、pp.25-26
29 パスカル、『パンセ』、p.225( 断章 347)
30 考えることは問うということである。問わなければ、動物と変わりがなく、生活しているだけになるから、そこに尊厳は生まれない。したがって、生きているだけが素晴らしいという主張は、人間だけの尊厳とはならない。
31 シェイクスピア、1983、小田島雄志訳、『ハムレット』、白水 U ブックス、p.174
32 佐藤透が二つの分類をしているので、それを元にまとめる。( 佐藤透、2012、『人生の意味の哲学- 時と意味の探求』、春秋社、p.89)
33 同上、pp.95-97
34 V.E.フランクル、2010、『夜と霧 新版』、みすず書房、pp.128-157
35 George Bernard Shaw、1903、Man and Superman( 邦訳は『人と超人』で喜志哲雄訳白水社 1993 年がある。)、p.174( 本文は wikiquote より引用) 日本語訳は、「人生には二つの悲劇がある。一つは夢を叶えることができなかったときである。もう一つは夢を叶えたときである。」( 筆者訳)
36 佐藤透、『人生の意味の哲学- 時と意味の探求』、pp.96-97
37 J.S.ミル、2008、村井章子訳、『ミル自伝』、みすず書房、pp.3-34,112-121

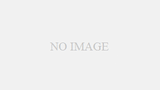
コメント