章ー節ー項
ex. 1-2-3 → 第1章の中の第2節の中の第3項
ex. 1-2→第1章の中の第2節
第1節:問いの意味 ←現在地
第1項:「意味」は何を意味するのか
第2項:「私」にとっての人生の意味
第3項:生きる手段と目的の違い
第2節:問いの発生過程
第1項:「問う」行為について
第2項:逆境における問いの発生
第3項:順境における問いの発生
第3節:人生の意味を問うことは有意味か
第1項:哲学的な問いとして
第2項:現代的な問いとして
第3項:普遍的な問いとして
第4節:人生の意味の必要条件
第1項:主観的かつ客観的納得
第2項:誕生肯定
第3項:絶対的な意味
第5節:幸福論
人生の意味と表現した時、それが何を意味しているかは様々に理解されうる。まず、本節では本論で扱う「人生の意味」という言葉が何を意味するかについて、分析哲学を中心に明確にする。浦田( 2013)によれば、「分析哲学の流れにおいて、ここ数十年( 特にこの四半世紀)の間に人生の意味の問題は、比較的厳密に検討されるようになってきている。そして、その際、問題となるのが、『人生の意味』という術語が何を意味するのか、とりわけ『意味』という語が、ここで何を意味しているのか、ということである」1。
第 1 項:「意味」は何を意味するか
浦田(2006)が Nielsen(2000)の言葉を引用しているように、人生の意味とは、「『蒙昧主義者』の意味とは何か」や「『机』の意味とは何か」、「『よい』の意味とは何か」というような語の定義や説明、記述を求めたり、指したりしているわけではない2。我々がここで人生の意味と言っているのは、問いという形で現れる人生の意味である。具体的には、「人間はどこからやって来て、どこへ行くのだろうか」という原因や結果としての問い、「必ず死んでいくのに、何のために(なぜ)生きるのか」という目的に関する問い、そして「人生は生きる価値があるのか(生きるに値するのか)」という価値への問いである3。これらの問いは、言語学的な「意味」を尋ねているのではなく、むしろ存在論的な「意味」を問うている。
さて、存在論的な「意味」を問うていると述べたが、それはどのようなことか。
「人生」とは、「人間として生まれ、生き、死ぬまで」のことであり、生まれた瞬間から死ぬ瞬間(心臓が止まる瞬間)までのことである。存在論的な意味と言っているのは、他の生物ではなく、人間に生まれてきた存在の目的、価値、意義のことである。したがって、本論で「人生の意味」と使うときは、「人生の目的」「生きる価値」「存在意義」と同義である。
次に「人生の意味」という問いについて、村山(2005)を参考に、行為と関連して問い自体の分析をする。人生とは、人間として生まれ、生き、死ぬということであり、そこに「◯◯ が」という主体を考えることができる。この点において、行為と人生は類似している。我々がある行為について「その行為の意味は何か」と問われた場合、それは「その行為を通じて、未来において何が実現されるのか」という未来の目的を問われていると捉えることができる。これを「人生」に適用すると、「人生の意味」とは、「人生を通じて、未来において何が実現されるのか」という問いとなる。この問いでは、人生(生きる)は手段と解釈できる。さらに、この問いは次のように書き換えられると村山は言う。「人生に手段や過程としての意味(価値・重要性)を与える、そのような目的は何か」。これは、人生が手段である以上、手段に対する目的がなければならないが、そのような目的は何かということである。しかもここでいう目的とは、手段-目的の連関が長い系列となったとしても、最終項には、それ自体で価値があるものがなければならず、それ自体は決して何かの「ために」あるのではない、究極的な目的が設定される必要がある。この目的を実現するための手段として、またはこの目的「のために」、人生は意味を与えられるのである4。ゆえに、人生の意味という問いは、目的が設定できたならば問いには答えが与えられたことになり、問い自体は生滅する5。また、究極的な目的は、手段- 目的の連鎖を目的の方に向かい、最終項にある ものをそのように呼んだのであるが、手段の方に遡ると第 1 項は「人生の意味は何か」という問いになると言われる。これは「究極のなぜの問い(the ultimate why-question)」と呼ばれ、ライプニッツ(Leibniz)以来問われてきた問いである6。故にすべてのものごと、行為の根拠に対する問いが「人生の意味(とは何か)」なのである。
第 2 項:「私」にとっての人生の意味
人生の意味の主語、主体は何であろうか。それは他人ではなく、「私」である。 人生の意味とは、この私が人間としてこの世界に生まれ、生きていくのは何のた めか、ということである。我々が人生の意味を考えるとき、それは決して誰かの 人生に意味・目的・価値があるかどうか( あったかどうか)を考えるわけではな い。例えば、アインシュタイン( Einstein)やマザー・テレサ( Mother Teresa) に人生の意味があったかどうかを問うているわけではない。外部から他人の人 生に意味があるかどうかということは本当の意味では言えないからである。確 かに、アインシュタインやマザー・テレサは、傍から見れば素晴らしい人生であ り、人生に意味はあったと言えるかもしれない。アインシュタインは科学の世界 で多大な貢献をし、マザー・テレサは他人のために人生を全うした。しかし、当 の本人たちが「私の人生に意味はあったのだろうか」と問うこともあり得るので ある。なぜなら、人生の意味の問いとは、森岡( 2015)の言うように「私が自分 自身の人生を生きていくことの真の充実を、その底から支えてくれる足場とな るものが実は不在なのではないかと実感したときに、心の底から叫ばれる問い」であるからである。つまり、外部から社会的な価値の有無を言うことはできても、人生の意味の有無を言うことはできない。その人自身が「それが私の人生の意味 だ」と思っているならば意味がないとは言えないし、「それは私の人生の意味で はない」と思っていればその意味を強要はできないからである7。
トルストイ(Lev Tolstoy)は外部からは一見、素晴らしい人生を送っていると思われていた一人であったが、その実は人生の意味を激しく求める一人であった。トルストイは日々感じていた疑問を『懺悔』で次のように描写している。 私の著作が私にもたらす名声について考える時には、こう自分に向って反問せざるを得なくなった。≪よろしい、お前は、ゴーゴリや、プーシキンや、シェークスピアや、モリエールや、その他、世界中のあらゆる作家よりも素晴らしい名声を得るかも知れない。- が、それがどうしたというんだ? …… ≫これに対して私は何一つ答え ることができなかった。この疑問は悠々と答えを待ってなどいない。すぐに解答しなければならぬ。答えがなければ、生きて行くことができないのだ。8
レフ・トルストイ
しかも、こうした状態が彼の身に起ったのは、「いかなる点から考えても全くの幸福と思われるとき」であった。愛し愛される善良な妻、かわいい子供達、莫大な財産、偽る必要のないほどの名声、そして精神的にも肉体的にも同年代では見られないほどの健康であった9。そのような状態にありながら、自らが何のためにと生きるのかという疑問が「何のために?」「で、それから先は?」と形を変えて、頻繁に現れるようになったのである。無益で幼稚と思っていた疑問が、いよいよ鎌首をもたげてトルストイの人生に迫ってきたのである10。この疑問をトルストイはこのように分かりやすく表明している。
私の疑問- 五十歳の時分に私を自殺させようとしたこの疑問- は、他愛のない小児から思慮分別の十分ついた老人に至るまでの、すべての人の心の中に横たわっている、最も単純な疑問であった。これを欠いては生きて行くことが不可能になる疑問であった。私はそれを実際に経験したのである。その疑問というのはこうだった。≪私が今行っていることや、明日も行うであろうことから、いかなる結果が生ずるのか?-私の一生涯からいかなるものが生まれるのか?≫
この疑問を別な言葉で表現すればこうなるであろう。≪何故に私は生きるのか、何故に私は何物かを求めるのか、また何事かを行うのか?≫さらにこの疑問はつぎのようにも言い現わせる。≪私の行く手に待ち構えているあの避け難い死によって滅せられない悠久の意義が、私の生活にあるだろうか?≫
レフ・トルストイ
普通の人が羨ましがるもの全てを揃え、他人から存在価値を認めらていたにも関わらず、トルストイ自身は人生の意味が全く分からず、これがなくては生きていられないと探し求めたのである。
また、実存主義の先駆けとも言われるキルケゴール( Kierkegaard)は、当時多くの人を魅了していたヘーゲルの体系建てた哲学を批判し、ピーター・ヴィルヘルム・ルンドへの手紙(1835 年 8 月 31 日)にこのようなことを書いている。
The thing is to find a truth which is true for me, to find the idea for which I can live and die.
キルケゴール
(私にとって真理であるような真理を発見し、私がそのために生き、そのために死ねるような真理を発見することこそが大事なのである。) 11
確かにヘーゲル哲学体系は、歴史、人生、生、死を説明しているが、それは抽象的な人間一般という次元であり、個々の「私」の生き死には全く問題にしていなかったのである。そのような客観的真理をヘーゲルが体系化したとしても、それは差し当たり「私」の主観的な真理にはならない。 また、カミュは『シーシュポスの神話』の中で、
人生が生きるに値するか否かを判断する、これが哲学の根本問題に答えることなのである。それ以外のこと、つまりこの世界は三次元よりなるかとか、精神には九つの範疇があるのか十二の範疇があるのかなどというのは、それ以後の問題だ。そんなものは遊戯であり、まずこの根本問題に答えなければならぬ。12
アルベール・カミュ
と言っている。トルストイ、キルケゴール、カミュにとって、人生の意味は一般的な問題ではなく、「私」の問題として逼迫していたのである。以上から、本論で扱う人生の意味とは一般論ではなく、「私」が人間として生まれ、生きるのは何のためかという主観的な問いである。
第3項:生きる手段と目的の違い
「私」にとっての生きる意味を考えるとき、注意しなければならないことがある。それは一見、このために生きていると思っているものが、生きるため( 生活するため)にしていることになっているという点である。例えば、「私は成功するた めに生きている」と言う人があるとしよう。成功とは、具体的に言えば、お金を儲ける、結婚する、試験に合格する、などである。しかし、前項のトルストイも 含め、多くの成功者が言うように成功は目的にはならない13。ラッセル(Russell)は『幸福論』に、具体的な成功例を挙げたあと、このように書く。
こうして、かわいそうに、この男は、成功した結果、途方にくれてしまうことになる。成功そのものが人生の目的だと考えられるかぎり、どうしてもこういう事態にならざるをえない。成功したあかつき、成功をどうしたらいいかを教えられていないかぎり、成功の達成が、人を退屈のえじきにするのはさけられないことだ。14
ラッセル
成功は、あくまで結果であり、本論で扱う人生の意味とは異なることが分かる。人生の意味とは、そのように成功して、どこに向かって生きていくのかということである。同様に、成長が人生の目的とする主張も本論で扱う人生の意味と言えないことが分かる15。
この違いを岸本英夫は、このように書いている。
人間の問題は、究極的には、二つの根本的な課題に、還元することができるように思う。すなわち、「人間はなんのために生きているか」という課題と、「人間は、どう生きてゆけばよいか」という課題とである。第一の「なんのために」という問題は、人生を、総合的にまとまった一つのものと考え、それ全体としての、目的やゆくえを問うているのである。第二の「どうすれば」のほうは、この世の人間生活のなかにおける、人間の根本的な態度としての、生きてゆきかたを、聞いているのである。16
岸本英夫
また、佐藤瑠威は、人間が意識存在であることによって、この二つの課題( 生き方と生きる意味)を不可避的に背負うと述べている17。
「なんのために生きているか」とは本論で扱う人生の意味を表し、「どう生きてゆけばよいか」というのは、生きる手段・方法であり、生きるためにすることを意味する18。私たちが日々、考え、行動しているのは主に「どう生きるか」についてである。飲食したり、勉強したり、友人と談笑したり、運動したり、睡眠をとったり、と毎日することは、ほとんど生きるためにしていることではないだろうか。お金を稼ぐ、有名になる、家族をつくる、これらはしなくても生きていけるが、よりよく生きるためにしていることには間違いないだろう。世間にあふれかえる How to 本は、まさしくどうすればよりよく生きられるかというために存在する。趣味や生きがいと言われるものも人生に趣や味をだし、生きる甲斐性を出すためにやるのではないか。しかし、「なぜ生きる」とは、それらをやって、生きていくのは何のためかということである。だから、トルストイが悩んだのも当然のことであり、我々は生きるためにしていることを生きる目的とすることはできないのである。それは前述の通り、生きるためにしていることは、手段-目的の連関が無限に遡行するものであるからである19。
エーリッヒ・フロム(Erich Fromm) は、「have の時代は終わった。これからは be でなければ駄目だ。つまり持つということから、存在する、あるということに価値を置きかえないと駄目だ」と言っている20。どう生きるかとは、まさしく、よりよく生きるために何かを持つ、もしくは do( する) ことである。しかし、どれだけ多くのものを持っても満たされず、苦しみも一向になくならない。世界に目を向けなくても、この豊かな日本だけを見ても同じである。持っていなくても、持っていても苦しむのに変わりはない。なぜなら、それは生き方の問題であるからで、完成のない、死ぬまで考えなければならないことであるからである。大事なことは be、すなわち存在の意味を知ることなのである。何かをしようがしまいが、何かを持っていようが持っていまいが、人生の意味が分かれば、関係なくトルストイのような問いは消え去るのである。
精神科医のフランクル(Frankl)『生きがい喪失の悩み』の中で、
けれども、実存的真空は生ずるのです。しかも、マスローのいわゆる基本的欲求のなかのどれひとつをも満足させずには残さなかった「ゆたかなる社会」の真ん中で生ずるのです。これは、この社会がまさに諸欲求だけを満足させているが、しかし意味への意志を成就していないことに由来します。「ぼくは二二歳です」と、私にあるとき、アメリカの大学生が書いてきました。「ぼくは学位をもち、ぜいたくな車を所有し、金銭的にも独立しており、またぼくの力に余るほどのセックスや信望も思いのままです。ぼくにわからないのはただ、すべてのものがどのような意味をもつべきかということだけです」と。21
フランクル
と、生きる手段は持っているが、生きる意味が分からない実存的真空( 実存的空虚)22について述べている。今や物が足りない「不足の時代」ではなく、物が溢れているのに何かが足りない「未足の時代」なのである23。アインシュタインが「手段は完全になったというのに、肝心の目的がよくわからなくなったというのが、この時代の特徴」であると言った24のは、まさにこのことである。生きる手段に不自由なく、栄養失調になることもなく、寿命も延び、医療技術の進歩により大方の病気は治ってしまう。しかし、そうやって健康になった体、延びた命で何をするのかがはっきりとしていないのである。それが人生の意味であり、人生の目的、なぜ生きるの答えなのである。
ここで、「何のために生きるかを考えることだけが大事だ」といっているわけではない。岸本が前述の後に、「何のために生きるか」と「どう生きてゆくか」は、あい関連し、ともに重要なものである25と言っているように、決してどちらか片方に重要性があるのではない。「どう生きてゆくか」だけしか考えていないかどうかを問題にしているのである。もし、手段についてしか考えていないとすれば、パスカルの言うとおり誠に嘆かわしい限りである26。
本節では、本論で扱う人生の意味の定義をした。本論で扱う人生の意味とは次のようなものである。
以下では、この定義を踏まえて、論を進めていく。次節では、一体どのような場合に問いが発生するのかについて論じる。
脚注
1 浦田悠、2013、『人生の意味の心理学 実存的な問いを生むこころ』、京都大学学術出版会、p.24
2 浦田悠、2006、「人生の意味についての理論的概観」、『教育方法の探求』、( 出版社要確認)、p.41
3 浦田( 2013) は、「意味」という語の意味について、分析哲学者の Hospers の 8 つ分類( 指示、原因、結果、意図、説明、目的、含意、意義) や Nozick の 5 つの分類( 外的な因果関係、外的な指示的・語義的関係、意図や目的、レッスン、個人意義・重要性・価値・問題) を取り上げている。[浦田( 2013)、p.25]
4 村山達也、2005、「人生の意味について- 問いの分析の観点から- 」、『哲学』第 113号、p.73
5 同上、p.77
6 菅沼聡、2004、「究極の問いの再考」、『哲学』、第 55 号、pp.179-182
この究極の問いは「なぜ、無ではなく、何かが存在するのか」という問いとしてもよく考えられるが、証明はされていない。本論では、「なぜ、存在するのか」ではなく、「何のために存在するのか」という問いである。前者は存在自体を問い、本論は存在する価値・理由を問うている。なぜ無ではなく、有なのかについては、主に扱うわけではないが第 3 章で言及する。
7 森岡正博、2015、「人生の意味」は客観的か: T・メッツの所説をめぐって 生命の哲学の構築に向けて(7)、『現代生命哲学研究』4、出版社、pp.87-90
8 トルストイ、1961、原久一郎訳、『懴悔』、岩波文庫、p.26
9 同上、p.29
10 同上、p.24
11 当サイト訳。出典は、Wikiquote( SØren Kierkegaard)。英語の文献では引用している文献が複数あったが、何が根拠になっているかまでは確認できなかった。また、ピーター・ヴィルヘルム・ルンドはキルケゴールの義理の兄弟である。
12 カミュ、2009、清水徹訳、『シーシュポスの神話』、新潮文庫、p.12
カミュはこの文章の前文に「真に重大な哲学上の問題はひとつしかない。自殺ということだ。」と書いているため、「人生が生きるに値するか否か」に結びつかないように思われる。自殺は、もちろん原因が究明され、多くは経済的な原因となっている が、根本的な原因は「こんなに苦しいのに何のために生きなければならないのか」という人生の意味の問いに帰結される。カミュはそのように考えていたから、次の文に 「人生が生きるに値するか否か」と続けたのだろう。
13 自己啓発の本では、成功は手段であり、目的と思ってはならないということがよく書かれている。例えば、『普通の人がこうして億万長者になった』(本田健) や『金持ち父さんの子供はみんな天才』(ロバート・キヨサキ) などである。『ボヴァリー夫人』で有名なフランスのギュスターヴ・フローベール(Gustave Flaubert) は、「成功とは結果であって目的ではない」と言っている。また、世界的に有名なジョン・レノンは「ビートルズは成功し、ツアーをやめ、欲しいだけの金や名声を手に入れ、最後に、自分たちは何も手にしていないことに気づいた」と言っている。挙げだせば例には切りがない。
14 ラッセル、2007、安藤貞雄訳、『幸福論』、岩波文庫、pp.56-57
15 成長とは、過程であり、目的にはならない。我々が問題にしているのは、成長してどこに向かうか、である。
16 岸本英夫、2011、『死を見つめる心- ガンとたたかった十年間』、講談社文庫、p.184
17 佐藤瑠威、2014、「哲学とは何か- 生きる意味の問題をめぐって- (1)」、『別府大学紀要』第 55 号、別府大学会、p.194
18 英語で「人生の意味」は、meaning of life と meaning in life の表記がある。浦田は meaning of life を人類や世界全体の存在理由に関する概念であるとして「人生の意味」と訳し、「meaning in life」は、個人的・日常的な価値に関する概念であるとして「生活の意味」と訳し、区別している。但し、先述の通り、日本語でもこの両者は区別されていないように英語でも区別されて使われているとは限らない( 浦田、 2013、p.43)。本論では「何のために生きるか」が meaning of life に、「どうやって生きてゆくか」が meaning in life に相応する。
19 「生きる」のは何のためか→お金のため( お金は何のためか) →食べるため( 食べるのは何のためか) →生きるため というように循環するものも多い。そうでなければ無限後退する。具体的な内容については、また後に詳述することになる。
20 小林司、1989、『「生きがい」とは何か- 自己実現へのみち』、NHK ブックス、p.72
21 V.E.フランクル、2014、中村友太郎訳、『生きがい喪失の悩み』、講談社学術文庫、 p.52
22 実存的真空とは、同 p.14 に、「フロイトの時代におけるように性的な欲求不満と対決しているわけではなくて、実存的な欲求不満と対決しています。また今日の典型的な患者はもはやアドラーの時代におけるように劣等感にさほど悩んでいるわけではなく、底知れない無意味感に悩んでおり、そしてこれは空虚感と結び合わされているので、私は実存的真空と呼んでいる」とある。フランクルによれば、実存的真空は、生きる意味への問いとなって現れるが、これは病理的なものではなく、「人間における最も人間的なものの表現」にほかならない。
23 松平実胤、1997、『喜び上手: 仏教に学ぶ生きるヒント』、鈴木出版、p159
不足の時代とは、物が足りず貧困な人が多かった時代である。しかし、今は物があふれかえり、不足はしていない。しかし、未だ何か足りない気持ちが出て来る。これを未足といい、今の時代は未足の時代であると言われるらしい。
24 ジェリー・メイヤー、ジョン・ホームズ編、2005、『アインシュタイン 150 の言葉』、ディスカヴァー・トゥエンティワン、p.37
25 岸本、『死を見つめる心』、p.184
26 パスカル、1999、前田陽一・由木康訳、『パンセ』、中公文庫、p.71
「すべての人が手段についてだけ熟慮して、目的についてそうしないのは、嘆かわしいことである。」(断章 98)

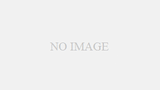
コメント